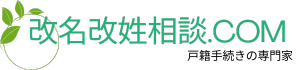出生届を提出したあと、「この名前で本当に良かったのか…」と迷いが生じることは、決してめずらしいことではありません。
実際にご相談を受ける中でも、「名づけを急ぎすぎたかもしれない」「もっとよく考えるべきだったかも」と感じている方は少なくありません。
乳幼児期であれば、改名は比較的柔軟に認められる傾向があります。法制度上も、すぐに結論を出さなければならないわけではありませんので、まずは冷静に気持ちを整理するところから始めてみてください。
ただ、一度改名が認められると、あとから「元に戻したい」と思っても、それが叶うとは限りません。だからこそ、焦らず、「本当に名前を変える必要があるのか」を丁寧に見極めることがとても大切です。
このページでは、「赤ちゃんの改名はいつまで可能?」「どんな理由なら認められる?」「手続きの流れは?」といった疑問について、司法書士の視点からわかりやすく解説していきます。
赤ちゃんにとって最善の道を選ぶための、ひとつの手がかりとしてご活用ください。
赤ちゃんの改名は可能?焦らず考えることが大切です

日本の法律では、原則として名前は変更できないとされています。しかし、「正当な事由」がある場合、家庭裁判所の許可を得て、名前を変更することができます。特に乳幼児期の改名については、柔軟に認められる傾向があります。
ただし、一度裁判所の許可を得て名前を変えると、「やっぱり元に戻したい」、「もう一度変更したい」と考えても、原則、許可は得られないので、「本当に今の名前を変えるべきか」は、じっくり考えることが大切です。
「この名前でいいのか」と悩まれている方にとって、焦らず判断するための助けになれば幸いです。この記事では、乳幼児の改名にあたって、制度や判断の視点について、司法書士の立場からやさしく解説していきます。
赤ちゃんの名前を変えたいと思う人は意外と多い
実は、赤ちゃん・乳幼児の名前を変えたいと考える人は意外と多いです。名前・氏の変更を専門に取り扱って、10年以上になりますが、乳幼児の改名のご相談は、常にご相談内容の上位です。
インターネット上では、赤ちゃんの名前の変更に批判的・否定的な意見も多いですが、実務上は裁判所の許可を得やすい傾向にあります。
ところが、許可を得やすいからといって、十分に検討しないで手続きを進めてしまったため、「やはり以前の名前のほうが良かった」、「やっぱり新しい名前がしっくりこない」と後悔する方もいらっしゃいます。
乳幼児期なら改名が認められやすい理由とは
名の変更は、原則として認められにくい制度ですが、乳幼児期に限っては比較的柔軟に許可される傾向があります。
実務の現場でも、「名付けに強い違和感がある」などの事情から申立てがなされ、裁判所により許可されている事例は少なくありません。
この章では、過去の裁判例をもとに、乳幼児期の改名において「正当な事由」がどのように柔軟に解釈されているのかを解説します。
名前の変更の一般的な基準
名の変更は、原則として認められにくい制度ですが、乳幼児期に限っては比較的柔軟に許可される傾向があります。
実務の現場でも、「名付けに強い違和感がある」などの事情から申立てがなされ、裁判所により許可されている事例は少なくありません。
この章では、過去の裁判例をもとに、乳幼児期の改名において「正当な事由」がどのように柔軟に解釈されているのかを解説します。
裁判所が改名のための「正当な事由」を認める一般的な基準は、以下のような裁判例が良く引用されます。
改名は正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て為しうべきことに定めた所以は、社会生活を営む個人の法律関係、戸籍関係に於ける特定性、同一性に着眼し、之が秩序を維持せんことを期し、之が秩序を維持することは、結局公共の福祉に適するものと考えたものであって、若し個人の恣意により、社会公共の見地より是認せられるべき合理的な必要性無きに拘わらず、濫りに改名が行わるることは、前記法律秩序を紊し、延いて公共の福祉に副はざにいたることを懸念したるに出たものであることが明らかである。
名は氏と共に人の同一性を示す称号たる機能を有するから、それがみだりに変更されないような公益的見地から呼称秩序の静的安全を確保することを前提とし、その呼称秩序の安定も、特定の個人が社会生活の必要から改名を希望し、従前の呼称を使用すると、その人の社会生活に著しい支障をきたしその継続を強いることが社会通念上不当であるような場合のみ、私益を公益に優先させ、呼称秩序の変動を許容しようといいのが法107条の法意である。
これらの裁判例を要約すると、以下の二つのポイントが「正当な事由」に対する裁判所の基本的な考え方だと言えます。
- 「個人が自由に、合理的な必要性もなく改名をすると、その人の特定性、同一性を判別することが難しくなり、社会的、公共的な混乱を招くので、これを防止することを目的に「正当な事由」が必要」
- 社会的な混乱を招いたとしても、「改名を希望している人に元の名前を名乗らせ続けることが社会的に不当である場合が「正当な事由」」
このような厳格な基準が、一般的な名前の変更に求められる「正当な事由」の判断基準だと考えられています。
一方で、赤ちゃんの名前の変更は、比較的柔軟に正当な事由が認められ、実務上、許可されやすい傾向にあります。
赤ちゃん、乳幼児の改名が許可されやすい理由
なぜ、赤ちゃん・乳幼児の改名が許可されやすいのかというと、「改名による社会的影響」が小さいため、「正当な事由」が厳格に適用されないことがあるからです。
一般的に名の変更のために「正当な事由」が求められるのは、「個人が自由に、合理的な必要性もなく改名をすると、その人の特定性、同一性を判別することが難しくなり、社会的、公共的な混乱を招くので、これを防止すること」とされています。
しかし、乳幼児であれば周囲の人間関係が親族などごく限定的なので、もし名前を変更したとしても、社会的・公共的な混乱はごく限られたものです。
赤ちゃん・幼児に関して、以下のような高等裁判所の裁判例があります。
近隣に約一か月違いで出生し、同じ幼稚園に入園している同姓同名者が居住していること、役場からくる書類も紛らわしく、今後一緒に進学することにより不便不都合が予想されること、いまだ幼少で名の上に築かれた社会関係は複雑であるとも言えない等原審判示の事情をも考慮して
父母の一方が他方に相談することなく勝手に命名した場合や父母間協議の結果と異なる名の届出をした場合は、他方がこれを追認しない限り、適法・有効な命名が合ったことにはならないというべきところ、本件では母が追認したことが認められず、また、子の福祉の観点のほか、抗告人は生後4か月の乳児であり名の変更による弊害が少ないことなどから名を変更することに「正当な事由」がある
これらの裁判例では、どちらも社会的な影響の少なさをあげています。ただし、社会的な影響の軽微のみで許可されているわけではなく、その他の個別の事情もあわせて考慮されている点には注意が必要です。
一度変更すると簡単には戻せない|急がないことが大切
赤ちゃん・乳幼児の改名が、裁判所の許可を得やすいことは間違いありません。だからと言って、急いで手続きをするべきではありません。
なぜならば、名の変更についての戸籍法107条2項
が氏名の安定性を確保し、社会秩序を守る観点から正当な事由を求めていることから、「再度の改名は、その本質上、原則として許すべきではない」とされているからです。この「再度の改名」には、全く新しい名前にすることと元の名前に戻すことの両方を意味しています。
例外的に再度の改名が許可されることもありますが、大人と同様に厳しく審査されるので、一度目の改名を急ぐあまり後悔する方もいます。
なお、赤ちゃん・乳幼児のころに両親が裁判所の許可を得て名前の変更をした人が、成人後に再度の改名をすることに関しては、子供の頃の改名は両親の意向であって自ら積極的に名の変更したわけではないので
ので、再度の改名として扱わないとする高等裁判所の判断があります。
赤ちゃんの改名はいつまでできるの?

赤ちゃんの名前を変えたいと考えたとき、「いつまでに手続きすればいいの?」「もう遅いのでは…」と不安になる方もいらっしゃいます。実務上は、赤ちゃんや乳幼児のうちは社会的な影響が少ないとされ、家庭裁判所の実務では、比較的柔軟に判断される傾向があります。
この章では、「赤ちゃんの改名はいつまでできるのか」という疑問にお答えしながら、年齢によって判断がどう変わるのか、また実務上の注意点についてわかりやすく解説します。
何歳までなら改名が認められやすい?年齢ごとの傾向
ご相談にいらした方から、「何歳までなら許可されるのか?」とよく質問されます。赤ちゃんや乳幼児の改名は、一般に認められやすいとされています。ただし、何歳までが「認められやすい」とされるのか、明確な基準があるわけではありません。実務上も、年齢だけで線引きされているわけではなく、個別の事情を踏まえて判断されています。
私の経験上、年齢はむしろ「正当な事由」があるかどうかを判断する際に、そのハードルを下げる一つの事情として考慮されていると感じています。
例えば、生後3か月であっても、「子供の名前がしっくりこない」といった主観的な理由でしたら、許可を得ることはできないでしょう。年齢はあくまで判断要素の一つにすぎず、逆に5~6歳だからといって許可されないわけではありません。
もし、しっくりこないといった主観的な動機であっても、通称を名乗っていることを理由にする改名を検討してみてください。
赤ちゃん・乳幼児は、通称を理由にする改名でも、大人よりもはるかに許可されやすいです。なぜならば、社会的な影響が小さいことが、その理由です。私の経験上・実務上は、2~3年程度の期間でも十分に許可される可能性があります。
「早い方がいい」とは限らない?判断のタイミングの考え方
赤ちゃん・乳幼児の改名は許可されやすい傾向があります。しかし、「早ければ早いほどいい」と一概に言えるわけではありません。
なぜなら、名の変更は原則として一度きりであり、再度の改名は裁判所に極めて厳しく判断されるからです。一度改名した後に「別の名前が良かった」「やっぱり戻したい」と思っても、簡単には認められません。
経験上、新しい名前の不満や「別の名前が良かった」等の後悔は、通称として名乗り、実生活で呼び名として使う/呼ばれることで、新しい名前の語感や親族等周りの人の反応を通じて、新しい名前への違和感等を確認することがで、ほとんど回避することができます。
通称を名乗り始めることをおすすめする理由は、他にもあります。
一つ目は、「正当な事由」とは言いきれないと裁判所が判断に迷う時でも、通称を名乗っていることが補助的に働いて許可をされることがあります。
二つ目は、裁判所が「正当な事由」に当たらないと判断しても、さらに数か月~1年、通称を名乗り続けることで、通称を理由として許可を得ることができます。
特に3歳頃までであれば、時間的な余裕は十分にありますし、5~6歳であれば万が一に備えて、まずは一定期間、通称として使用してみることを強くおすすめします。何度も手続きをすることなく、1回でお子様の名前の問題をしっかりと解決することが、なによりも大切だと考えています。
「訂正」と「改名」はどう違うの?
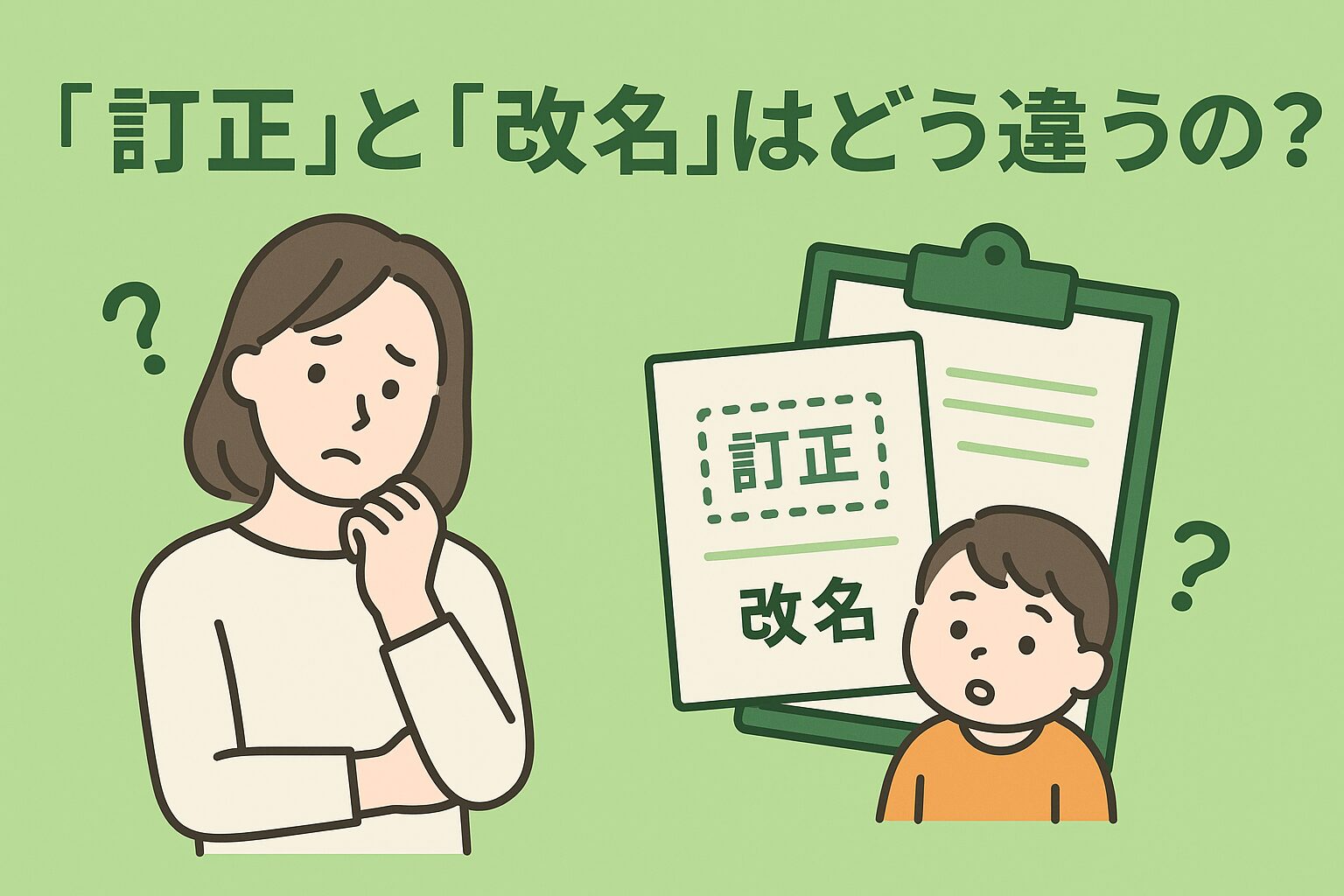
赤ちゃん・乳幼児の名前を変更したいというご相談者の多くが、戸籍訂正の手続きですることはできないかと質問されます。
確かに戸籍訂正であれば、戸籍の記録の方式が違うので、転籍等の手続きで新しく戸籍を作ったときに、訂正の記録が見えなくなり、お子様にわかりにくくなるといったメリットがあります。
もっとも、戸籍の記載に誤りがあったり、戸籍の届出が無効である場合は「訂正」で対応できることもあります。しかし、この証明は実務上かなり困難で、このため、「改名」の手続きを選択することが一般的です。
戸籍に誤記がある、出生届が無効である場合は「訂正」で対応できます
本当に「改名」の手続きが必要でしょうか?もし、出生届の手続きが法律上無効である場合、戸籍の記載が誤りである場合等、「訂正」の手続きによって対応できることがあります。
第113条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
具体的には、以下のようなものが考えられます。
- 事前に決めていた名前を出生届に記入するときにうっかり間違えた。
- 両親で命名の意見が一致しないまま、片方が勝手に出生を届け出た。
- 義理の親が勝手に出生届を役所に提出していた。
「出生届の記入を間違えた」場合
「出生届の記入を間違えた」場合は錯誤にあたりますが、事前に決めていた名前を証明する必要があります。しかし、「翔平」を「晋太郎」と間違えたというのは、認められないでしょう。
また、誤記に関しての戸籍訂正の裁判例は、戸籍訂正の手続きを認めたケースと改名の手続きを認めたケースに分かれています
戸籍届に誤記があるからと言って必ず訂正が認められるわけではなく、証拠資料によって訂正、改名のいずれかを選択することになります。あるいは戸籍訂正について裁判所の判断をあおいで、場合によっては訂正を取り下げて、改めて名の変更を申し立てることになります。
ただし、訂正を認められている例は、特殊な事情が存在しているので、難易度は高いと考えられらます。
「片方が勝手に出生を届け出た」場合
「片方が勝手に出生を届け出た」ケースは、前述の昭和12年5月29日の大阪高等裁判所の裁判例の他に、いくつかの裁判例があります。(例:函館家庭裁判所、昭和45年10月22日の審判;那覇家庭裁判所、昭和48年10月30日の審判;山形家庭裁判所鶴岡支部、昭和57年11月29日の審判)
しかし、これらの裁判例はいずれも戸籍訂正ではなく、名前の変更を許可したものです。
「義理の親が勝手に出生届を役所に提出していた」場合
父母の意志が一切反映されず、新生児から見て祖父又は祖母が独断で出生を届出た場合は無効です。この場合も、どうやって祖父又は祖母の独断であったのかを証明することが困難です。
市区町村が間違えた場合
ごくまれに、出生届に記入した名前を戸籍に記録するときに、市区町村の担当者が間違うこともあります。
こういった場合は、裁判所の手続きは不要で、市区町村に出生届のコピーを持参して、誤りを指摘してください。市区町村の職権で、戸籍の訂正をすることができます。
第24条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない
2項 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。
3項 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。
名前の訂正や改名について迷われたときは、無理に一人で判断せず、まずは専門家にご相談ください。実際の証拠や状況に応じて、どちらの手続きが適切かを丁寧にご案内いたします。
名付け後に「やっぱりこの名前は違う」と感じた場合は「改名」の対象です
赤ちゃんの名付けの後に「この名前、やっぱり違うかも」「なんとなくしっくりこない」と感じることは、決して珍しいことではありません。
ただし、こうした理由だけでは戸籍の訂正はできません。訂正の手続きは、出生届に明らかな誤りや無効の原因がある場合に限られます。
そのため、名付け・出生届に問題がなかった場合は、「改名」の手続きによって対応することになります。
実際には、「保育園では別の名前で呼んでいて、戸籍の名前と齟齬がある」「家族や周囲に混乱がある」「赤ちゃん・乳幼児の日常生活に支障をきたす」等の事情を丁寧に整理すれば、家庭裁判所で許可が得られる可能性が十分にあります。不安がある場合は、専門家に相談されるのも良いでしょう。
「訂正」は不適切な戸籍記録の是正、「改名」は名前そのものを変更する制度です
赤ちゃん・乳幼児の名前の変更のご相談の際に、戸籍の訂正で対応できないかとご相談を受けることも少なくありません。
なぜなら、戸籍の訂正であれば、訂正後に転籍などの手続きをすることで、戸籍を訂正した記録が目立たなくなるため、お子様本人にとっても心理的な影響が少ないというお考えもあります。
ですが、「訂正」と「改名」は、結果として同じように新しい名前が戸籍に記録されるという点で似ていますが、制度としてはまったく異なる手続きです。
「訂正」は、戸籍の記録に誤りがあったとき・出生届が無効であったときに、その誤りを正すための手続きです。一方、「改名」は、戸籍の記録が法的に正しくても、「正当な事由」があるときに名前そのものを変更する制度です。
どちらの手続きが適しているかは、「名前が間違っているのか」「名前を変えたいのか」によって大きく異なります。
「訂正」と「改名」の難易度の違い
手続きを選択するときに、特に問題になるのが、訂正の手続きの難易度の高さです。
赤ちゃん・乳幼児の名の変更の手続きの場合、「正当な事由」の証明は、今までみたとおり、過去の裁判例や実務上の取り扱いで「正当な事由」とされる範囲が広く認められています。
しかし、戸籍訂正の手続きは、必ず出生届に誤りがあったこと、出生届が無効であることを証明する必要があり、また、出生届に誤りがあった場合であっても、改名の手続きによる場合もあります。
手続きの解説書では、「正当な事由」と「誤記又は無効」の証明をしやすい方の手続きをすれば良いとされていますが、実際には無効・誤記の証明は難しく、誤記を証明できる場合でも改名の扱いになることもあり、戸籍の訂正をすることのハードルはとても高いです。
そのため、実際には改名の手続きを選択される方が多いです。
どんなときに赤ちゃんの改名が認められる?

「この名前、やっぱり違うかもしれない」出生の届出から時間が経つにつれて、そう感じ始めることも決して珍しくありません。実際、読み方の違和感や呼びにくさ、家族や保育園での呼び名とのズレに戸惑いを感じる方は少なくありません。
とはいえ、赤ちゃんの名前を変えるには、家庭裁判所の許可が必要です。許可を得るには「正当な事由」が求められますが、赤ちゃん・乳幼児の改名の場合は、過去の裁判例や実務上の運用から、比較的認められやすい傾向にあります。
たとえば、「通称として戸籍の名前とは別の名前を使っている」「周囲との混乱が生じている」「赤ちゃんの養育に支障をきたしている」などの事情があれば、家庭裁判所で改名が認められる可能性が十分にあります。
このほか、早期の名前の変更が本人や家庭にとって望ましいと判断される事情も、「正当な事由」として重視される傾向にあります。
名付けに対する違和感や不適切さを強く感じている場合
出生の届出後、「この名前、思っていたイメージと違ったかも…」「名付けに失敗した」「キラキラネームではないか気になる」と感じ始めることは、実は珍しくありません。読み方の響きやバランス、周囲の反応などから、少しずつ違和感を持つようになる方も多くいらっしゃいます。
そうした違和感が深まり、子育てや日常生活に影響があり、赤ちゃん・乳幼児本人のためにならないといった場合は、「正当な事由」があると認められ、改名が許可される可能性があります。
思い悩み、たとえば育児が全くできないといった状況は、赤ちゃん本人に差し迫った危機があり、正当な事由に該当すると判断されやすいです。
ただし、「違和感がある」「この名前は少し不適切かもしれない」といった感覚だけでは、家庭裁判所が「正当な事由」として認めることは困難です。
日常生活に実際の支障があって、それが赤ちゃん本人にどのような不利益を及ぼすかが重要な判断要素になります。
違和感等があるけれども、本人に不利益がないような場合は、正当な事由を認めてもらうことは難しく、通称の使用と併用しながら準備することをお勧めします。
「改名を考えること自体が悪いことではありません。悩まれた場合は、一人で抱え込まず、医師などの専門家に相談することも選択肢のひとつです。」
名付けの経緯に納得できず、父母の意思の不一致・対立がある場合
「名づけに慎重になりすぎて、期限ギリギリにあせって出生届を出してしまい、後悔している」「本当は一緒に考えたかったのに、配偶者の一存で名前が決まってしまった」、名付けに関して、出産前後のあわただしさでしっかりと名付けられなかった場合や、父母の間で気持ちのすれ違いや対立があった場合、その経緯が大きな後悔や心のしこりとなることもあります。
こうした事情が赤ちゃんに大きく悪影響を及ぼすと判断されれば、改名の「正当な事由」として認められることもあります。とくに父母間の対立が深刻な場合で、育児に支障がある状況では、裁判所でも柔軟な判断がなされることがあります。
出生届の赤ちゃんの名前の欄については、役所にまだ名前が決まっていないことを伝えて、後日、名前を補完することも可能です。しかし、出産直後はとにかくあわただしく、納得しきれない名前を記入してしまうこともあります。
父母の間で意見が一致していない場合や、電話や口頭で話し合っていたために父母が考えていた漢字がずれていて、片方が相手の考えていた漢字ではないものを記入することもあります。
こういった場合は、特に父母の感情的な行き違いが大きくなりやすく、戸籍上の名前のままでは赤ちゃんの生活が立ちいかないことも起こります。重大なケースであれば、父母の離婚にまで発展することもありますし、後悔が深く父母がうつ病などになってしまうこともあります。
「名付けに対する違和感や不適切さを強く感じている場合」と同じように、赤ちゃんの不利益の程度が許可に大きく影響しますが、特に父母の対立が深刻な場合は裁判所に「正当な事由」を認めてもらいやすいです。
名付けの経緯に納得できないまま、日常生活や育児にまで悪影響が及んでいる場合は、赤ちゃん本人にとっての不利益が強く認められ、裁判所でも実情に即した判断が期待できます。
通称やハーフの子の外国証明書の不一致で、赤ちゃんの生活に支障がある場合
「家族の間では別の名前で呼んでいるけれど、戸籍と違っていて困っている」「外国で発行された出生証明書の名前と、日本の戸籍の名前が一致せず、手続きのたびに説明が必要…」、こうしたお悩みを抱えるご家庭も少なくありません。
家庭内の通称や外国書類との不一致が、赤ちゃん本人の生活や手続きに支障を及ぼしている場合、家庭裁判所では改名の「正当な事由」として認められることがあります。
「家族の間では別の名前で呼んでいる」場合
家族の間では別の名前で呼んでいる場合は、通称の使用による改名にあたります。成人の場合であれば、長期間、通称を名乗っていることが求めらえます。
ところが、赤ちゃん・乳幼児の場合は、実務上2~3年程度でも許可される可能性があります。ただし、通称を使っている範囲が家族だけ、親戚だけといった場合は、認められる可能性がとても低いです。
幼稚園の関係者、両親の友人や習い事などで通称を名乗る範囲を広げて、たとえば、幼稚園の連絡網に通称が記載されている場合は有力な証拠になるので、こういった資料を多く集めましょう。
家庭外でも広く通称を名乗っていることの証拠資料をしっかりと集め、裁判所に理解してもらえれば、許可を得ることは難しくありません。
「ハーフの子の外国証明書との不一致」の場合
国際結婚での出産で、赤ちゃんが複数の国籍を持つ場合、日本の戸籍に記載された名前と外国の出生証明書や身分証明書等と一致しないことがあります。たとえば、ミドルネームが日本の戸籍では一部が省略されていたり、あるいは一致しないことも起こりえます。
こうした不一致があると、特に外国への出入国や将来のキャリア形成で障害になり、説明や追加書類の提出が必要となることもあります。また、日常生活においても名前の使い分けを強いられ、お子様本人が混乱することもあり得ます。
家庭裁判所では、このような「身分証明書上の不一致」が原因による公的手続の障害は、「正当な事由」として改名の許可が認められる可能性が高いです。特に、近年は出入国時の審査を厳格化している国もあり、影響が大きくなるのではないかと考えられます。
日本国籍と外国籍をもつハーフのお子さんを育てるご家庭では、各国の証明書の整合性を保ち、混乱を避けるという観点から、改名による対応を検討される方も少なくありません。
改名の手続きと準備の流れ

赤ちゃんの改名を検討される方の中には、日常生活の中で少しずつ名前に違和感を感じたり、名付けの経緯に納得がいかなかったりと、さまざまな事情を抱えていらっしゃいます。
改名の手続きは、家庭裁判所への申立てを中心とする法的な手続きとなりますが、あらかじめ流れを把握しておくことで、落ち着いて準備を進めることができます。
この章では、司法書士としての実務経験にもとづき、赤ちゃんの改名申立てに必要な手続きや書類、準備のポイントをできるだけ分かりやすく解説します。
赤ちゃんの改名にも家庭裁判所への申立てが必要です
赤ちゃん・乳幼児の改名も、戸籍法107条の2の手続きが必要になります。
第107条の2 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。
ですので、まずは家庭裁判所に名前を変更することの許可を求める申立をして、許可を得た後に市区町村へ名及び振り仮名を届け出ることになります。
家庭裁判所は、申立書と添付された証拠資料から事情を調査して、申立てをした当事者との面談(予備審尋と呼ばれます)で裁判所が抱いている疑問点や書類からはわからない事情を聴きとります。
そして、正当な事由があるかどうかを審査し、正当な事由があると判断すると、名及び名の振り仮名の変更を、裁判所は正式に許可します。
もし、申立書と証拠資料からは正当な事由がないと考えるようであれば、どういった理由で正当な事由がないと判断したかを明記した却下の審判をします。
正当な事由があるとも、ないとも言い切れないと判断に迷うようであれば、追加の証拠資料の提供を当事者に求めます。
必要書類と証明資料のそろえ方
次に、申立ての準備を始めるにあたって、必要な添付書類を確認しましょう。
家族全員分の現在の戸籍
必ず必要になるのは、家族全員が記録されている現在の戸籍です。
戸籍を請求するためには、本籍と筆頭者の情報が必要になります。本籍・筆頭者が不明確な場合は、本籍筆頭者の記載のある住民票を取得して確認する必要があります。
以前は、本籍地の市区町村でなければ戸籍を取得できませんでしたが、令和6年3月以降は、どの市区町村でも「戸籍の広域交付」の制度で取得できます。
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニ交付のサービスで取得することができます。(手数料が割安に設定されています。)
「正当な事由」を証明できる資料
裁判所は証拠資料にもとづいて「正当な事由」の有無を判断します。ですので、これを証明できる資料も用意しなければなりません。
具体的には、個々の事情で違うので、以下に代表的な事例を挙げて説明します。
なお、いずれの場合であっても、通称を名乗っていることの資料は、有利になりますので、並行して集めることを強くお勧めします。
キラキラネームを理由にする場合
キラキラネームである/キラキラネームではないかと思い悩んでいる場合は、戸籍に記録されている名前と名の振り仮名そのものが証拠になりえます。
この他に、これが原因で起こっている不都合を証明できる資料があるとなお良いですが、存在しない場合は申立書で具体的に説明する必要があります。
また、令和7年5月26日以降、出生時に名の振り仮名も届け出るように戸籍法が改正されているので、今後、キラキラネームを理由にすることはできなくなる/難しくなるのではないかと思います。
名づけを間違えたと感じている場合
名づけ間違えについては、いくつか要素があります。
名づけを間違えたことを証明できる資料というのは、原則存在しないはずです。証拠ではなく、なぜ間違えたと考えているのかを申立書で説明することになります。
次の要素は、間違えによって発生している不利益の証明です。これは証拠があるとは限りません。例えば、思い悩むあまり精神疾患を発症したり、産後うつの症状が悪化などがあれば、医師の診断書等がこれにあたります。そうでない場合は、同じように申立書で具体的に説明しなければなりません。
最後の要素は、赤ちゃん・乳幼児の名前を変更する必要があることの証明です。これも証拠資料があるとは限りませんが、「改名をしても不利益が解消されない」ことはないという説明をする必要があります。
父母の意思の不一致・対立を原因にする場合
父母の意志の不一致・対立を原因にする場合は、基本的に証拠は存在しないので、どういった経緯で意見が分かれ、改名をしようと決断したかを丁寧に説明する必要があります。
しかし、意見の対立が深まり、離婚にまで至っているようでしたら、戸籍に離婚の記録がされています。この他に離婚時に取り交わした書類(財産分与など)で経緯がわかるようであれば、その書類は証拠資料になるでしょう。
裁判所の手続きで離婚をしている場合は、裁判所に記録があるはずなので、どこの家庭裁判所の事件番号(令和〇年(家イ/家ホ)第×××号といった番号)の手続きであったかを明記するのも良いですし、裁判所の調停調書/判決書のコピーを用意することも良いでしょう。
通称を理由にする場合
通称を名乗っていることを理由にする場合は、証拠資料の質と量がとにかく重要です。しかし、成人と比べれば厳しくありません。
例えば、保育園や幼稚園、一時預かりなどとのやり取りや、親戚友人などのとのやり取り、イベントごとに参加した記録など、幅広く新しい名前を名乗ることで、有力な資料が蓄積しやすくなります。
保育園の名札や連絡帳、ラインなどアプリの通知やメッセージ、メール、郵便物、写真、印刷物、ギフトや記念品など、法定の資料や形式はありませんが、幅広く名乗っている必要はあるので、様々な人から資料を集めることが望ましいです。
通称を理由にする場合は、改名をしたい動機の部分は重視されないので、申立書で軽く触れる程度でも十分です。
外国の証明書との不一致を理由にする場合
外国の証明書との不一致を理由に必要になる証拠資料は、第1にその外国の証明書(パスポートや出生証明書)です。加えて、その証明書の日本語訳も必要です。翻訳は誰がしてもかまいませんが、末尾に「正しく翻訳しました」と追記して署名押印する必要があります。
不一致を原因とした不利益についての書類があれば、これも証拠資料なりますが、具体的な事情を申立書で説明しても十分だと思います。
「申立ての理由」「正当な事由」の書き方と伝え方の工夫
必要な戸籍や証拠資料がそろったら、次は家庭裁判所に提出する「申立書」の作成に進みます。ここでは、申立書の『申立ての理由』について、構成の考え方や裁判所に伝えるための工夫を紹介しています。
申立書には、名前を変えたいと考えた動機や名前を変えなければならない「正当な事由」を丁寧に説明することが求められ、これをどの資料で裏付けて証明するかも考えなければなりません。
どこまで書くべきか、どう伝えれば伝わるのかと迷う方も少なくありませんが、表現を工夫することで事情が正確に伝わり、スムーズな審査につながる可能性が高まります。
一方で、主観的すぎる表現や抽象的な理由だけでは、裁判所に伝わりにくいこともあります。
ここでは、申立書を作成する際の基本的な考え方や、実際に書くときの工夫についてご紹介します。
「申立ての理由」のポイント
申立ての理由は、改名を希望する動機とその必要性を伝える、申立書で最も重要な部分です。
一般的な文章の書き方でいう起承転結のうち、起と承、結があれば十分です。
最初の起の部分は、いつ、だれに、なにが起こったのかをシンプルに書いていけば大丈夫です。不安があれば、時系列に沿って出来事を列挙していくのも良いでしょう
次の承の部分はとても重要です。起の部分が原因で、赤ちゃんにどういった支障が発生しているのかを説明していきます。
最後に結の部分で、この問題を解消するために名前を変更する必要があることを筋道をたてて説明します。
成人であれば、証拠資料で具体的に証明する必要がありますが、赤ちゃん・乳幼児の改名であれば、成人ほど厳密に求められるわけではありません。
「正当な理由」のポイント
「正当な理由」は、申立ての理由の前述の承と結の部分です。
子供の名前が原因で、子供に不利益・不都合が発生していて、これを除くには名前を変更する必要があると、裁判官を納得させなければなりません。
特に名前と不利益等の客観的な因果関係が大切です。未成年の場合は緩やかに判断される傾向があり、障害になることは少ないですが、因果関係が薄く、仮に名前を変えても問題が解決しないと裁判所が考えれば、許可を得ることは難しいです。
「どんなときに赤ちゃんの改名が認められる?」の部分であげた典型的な例でなくても、名前と不利益等の客観的な因果関係と改名の必要性が強ければ、改名の許可を得ることは難しくありません。
迷っているときに考えておきたいこと

赤ちゃんの名前を変えるかどうか──それは、感情だけでなく、日々の暮らしや法的な手続にも関わる、慎重な判断が求められるテーマです。名前を変更した後にやり直すことは難しく、判断には時間をかけることが大切です。
無理にすぐ結論を出す必要はありません。迷いや不安を抱えるのは当然のことであり、手続きを1年、2年と遅らせたとしても、問題ないケースがほとんどです。
まずは、「改名が本当に子供のためになるのか」「新しい名前は本当にこれでよいのか」をじっくりと考えて、お子様にとって最善の選択を慎重に模索していくことが大切です。
この章では、改名に踏み切るかどうかを考えるうえで、整理しておきたい視点や思考の手がかりをご紹介します。
改名するかどうかの判断ポイントとは
判断のポイントはご家庭によって異なりますが、緊急性や必要性が高い場合は、お子様のために冷静に検討し、場合によっては速やかに対応することが求められるかもしれません。
例えば、「ハーフの子の外国証明書との不一致」のように、将来的に出入国などで手続き上の支障が懸念されるケースでは、改名の必要性が高いと言えるでしょう。
また、「父母の意思の不一致・対立」が深まり、お子様への心理的負担や家庭の安定に影響が出ているようであれば、慎重ながらも前向きな検討が必要になるかもしれません。
一方で、通称使用の実績を理由に改名を考える場合は、資料の蓄積に時間がかかるため、すぐに手続きを進めるのは難しい場合もあります。
いずれにしても、主観的な思いだけでなく、「赤ちゃんにとって本当に必要な改名かどうか」を客観的に見つめ直すことが、納得のいく判断につながります。
気持ちの整理と家族との話し合いのすすめ
赤ちゃんの改名の手続きは、感情的な揺れや戸惑いの中で検討されることが少なくありません。とくに名前の変更のやり直しが難しく、拙速な決断は避けるべきです。
お子様にとって、将来的な生活や人間関係に影響が生じることもあるため、冷静な気持ちの整理と、家族間での基本的な認識の共有をしておくことが望ましいでしょう。
相談できる専門家に話をしてみるのも選択肢です
赤ちゃんの改名を検討する過程では、法的な準備だけでなく、家庭内の対話や感情面での整理が必要になる場面も少なくありません。とくに考えがまとまらないときは、一人で抱え込まず、相談できる窓口に頼るのも一つの方法です。
例えば、お住まいの自治体の「子育て支援窓口」「家族相談支援センター」といった福祉・子育ての窓口では、家庭内の問題について中立的な立場で相談を受けられることもあります。
必要に応じて、産婦人科・精神科や臨床心理士・カウンセラーといった専門職が対応できることもあるでしょう。
判断を急がず、安心して進めていくためにも、こうした外部の支援を活用することは有効です。
まとめ|焦らず考えること、そして赤ちゃんにとっての最善を

赤ちゃんの名前を変えるかどうか──それは、感情だけでなく、日々の暮らしや法的な手続にも関わる、慎重な判断が求められるテーマです。名前を変更した後にやり直すことは難しく、冷静に判断をすることが大切です。
無理にすぐ結論を出す必要はありません。迷いや不安を抱えるのは当然のことであり、手続きを1年、2年と遅らせたとしても、問題ないケースがほとんどです。
「今はまだ決めきれない」──そんな気持ちを抱えている方こそ、焦らずに整理する視点を持つことで、必要な準備や選択のタイミングが見えてくることがあります。
赤ちゃん・乳幼児の改名手続き自体は、あまり難しくありません。だからこそ、しっかりと検討し判断することで、たとえ時間がかかったとしても、その選択はきっとお子様の未来につながるものとなるでしょう。
問い合わせてみる赤ちゃんの改名を考えたときのよくある質問
-
赤ちゃんの改名には、どんな手続きが必要ですか?家庭裁判所の許可は必要ですか?赤ちゃんの名前を変更する手続きは、戸籍法107条の2の手続きが必要で、家庭裁判所の許可を得て、名及び名の振り仮名の変更を届け出なければなりません。
申立て後、裁判所からの照会書などに回答し、許可が下りたら、市区町村に戸籍届を出します。詳しくは「改名の手続きの流れ」の章もご覧ください。 -
申立てはどこの家庭裁判所にすればいいですか?手続き後の届出先も教えてください。申立ては、原則、赤ちゃんの住民票がある市区町村を管轄する裁判所に申立てます。「〇〇県」「家庭裁判所」「管轄」といったキーワードで検索すると裁判所のページが見つかります。名及び名の振り仮名の変更は、住民票のある市区町村又は本籍地の市区町村に届け出ます。
-
改名後、母子手帳や健康保険証などはどうなりますか?国民健康保険であれば、名の振り仮名の変更届後、住民票が書き換わるタイミングで保険証が切り替わるので別途手続きをする必要はありません。国民健康保険以外の健康保険の場合、従前は新しい戸籍を添付して手続きしていたようですが、近年はマイナンバーと連動しているので、新しいものが送られてくるそうです。母子手帳は特別規定がないようです。
-
読みにくさや漢字の複雑さを理由に改名はできますか?読みにくさ、漢字の複雑さの程度によりますが、人名用漢字であれば難しいと考えられます。また読みにくさについても、令和7年5月26日以降、出生届の審査内容になったので、同様に難しいと考えられます。しかし、他の事情と複合的に認められることはあります。
-
名前をつけたあとに後悔した場合でも、改名はできますか?名付けに後悔があること自体は、「正当な事由」にあたりません。
感情や心情だけでは難しいものの、日常生活上・育児上の支障が出ていれば、実害があるとして認められる可能性があります。 -
通称を使っているだけでは、改名は認められませんか?通称を名乗っていることは「正当な事由」として認められることがあります。乳幼児であれば2~3年程度の期間とこれを証明できる資料が相当量必要です。
-
赤ちゃんの改名は、何歳までに行うべきですか?特に制限はありません。「正当な事由」を裁判所が認めさえすれば、改名の許可は得られます。ただし、4~5歳くらいですと難易度が上がります。
-
名前を変えないで様子を見る、という判断もできますか?はい。様子を見ることも一つの選択肢です。仮に小学校に入学した、中学校に進学したとしても、改名が不可能になるわけではありません。
-
両親の意見が割れている場合でも、改名手続きは可能ですか?乳幼児の場合は単独で手続きをすることができず、必ず親権者全員が手続きする必要があります。ですので両親で意見が一致しない場合は改名手続きをすることができません。ただし、離婚で単独親権者になっている場合は、一人の親権者だけで手続きすることができます。
-
改名の理由を将来、子供にどう伝えればよいですか?法律的にこうするべきというものもなく、正解はないと思いますが、正直に話すのが良いと思います。
-
改名について、司法書士などの専門家に相談するメリットはありますか?専門家に相談することで、知識と経験にもとづいた的確なアドバイスを受けられます。
-
医師やカウンセラーの意見書が必要になることはありますか?法定の添付書類ではありませんが、「正当な事由」を証明するために必要であれば、診断書や意見書を取得するべきです。
-
改名のことで悩んでいるとき、どこに相談すればよいですか?手続的なことでのお悩みであれば弁護士など法律専門家に相談すると良いでしょう。日常生活や体調でお悩みでした行政、医師やカウンセラーに相談すると良いでしょう。