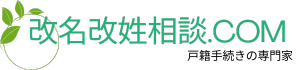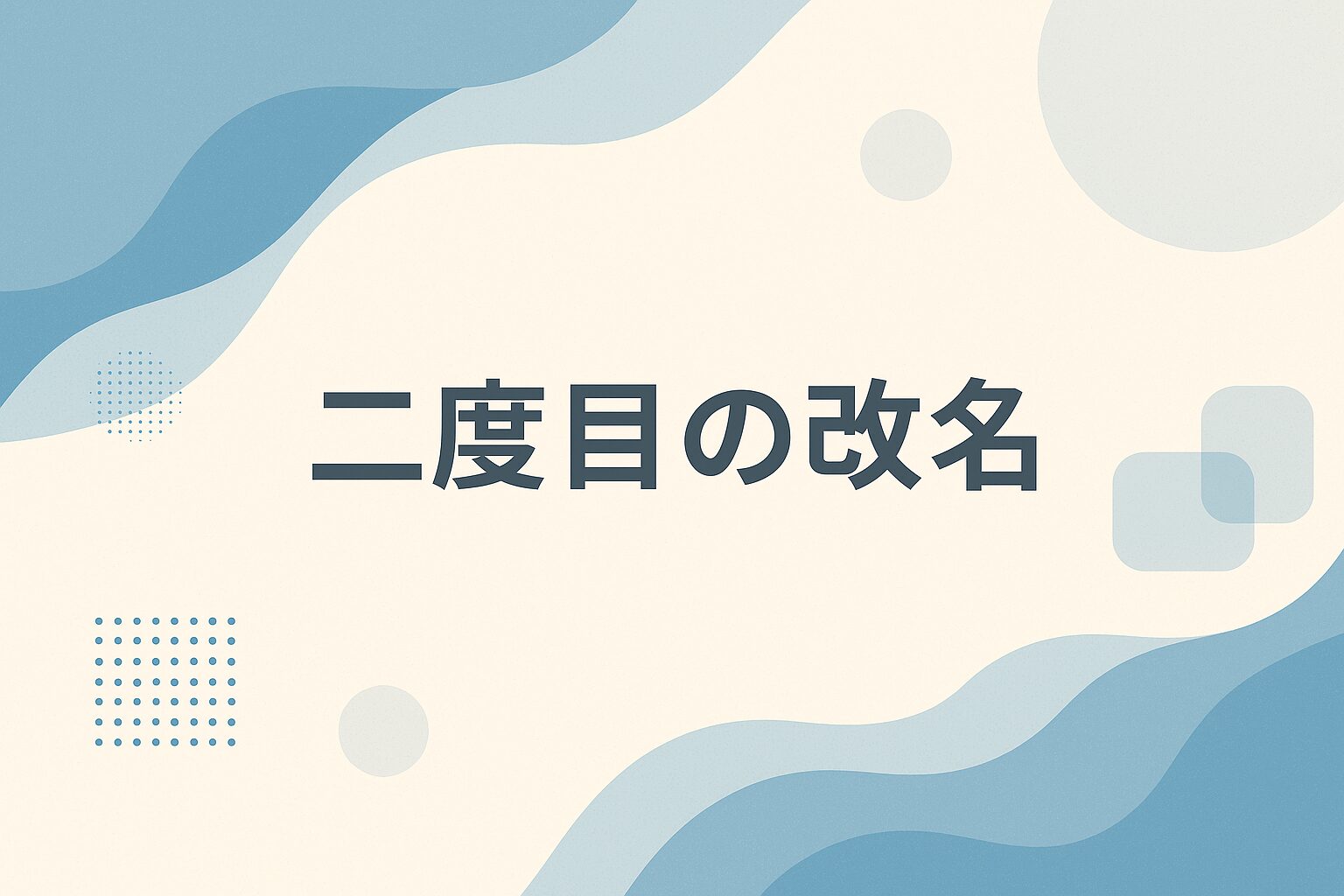
一度裁判所の許可を得て名前を変更した後に再度の改名をすることは、法律上不可能ではありませんが、原則として認められません。生活に大きな支障が生じるなど特別な事情がある場合にのみ、例外的に許可されます。本記事では代表的な裁判例と注意点を整理します。
再度の改名に関する原則的な判断基準
まずは、一度裁判所の許可を受けて戸籍上の名前を変更した後、再度、改名のための許可を得ることができるのか、原則的な取り扱いを確認します。
昭和38年と古い家庭裁判所の審判例ですが、現在でも意味があるものだと考えられるので紹介します。
一度裁判所の許可を得て名前を変更した後に重い病にかかり、周囲から「名前が悪い」と指摘され、それから10年以上にわたって新しい名前を通称として名乗っていたという事例です。
家庭裁判所は、一般的な基準として、以下のように示して、原則として許可されないと判断しました。
戸籍法第107条は正当な事由ある場合家庭裁判所の許可を得て改名することができる旨規定しているのみであるから、別に再度の改名を許さない旨明文があるわけではない。しかしながら名が個人の表象として氏と共にその人を他の者から識別する機能を果していることに鑑みるなら、その名を度々変えることはその個人に対す在社会の同一性の認識を不明確ならしめ、ひいては社会生活上混乱を招くものであるからその本質上原則として許されるべきではないといわなければならない。
そして、例外として許可することができる場合も示しています。なお、この審判では例外にあたるとして許可をしています。許可をした理由は、次の章「通称を名乗って生活していたことを理由に再度の改名が許可されたケース」で詳しく説明します。
唯例外として、再度改名の必要性があり、しかも改名の結果個人の同一性の認識が著しく困難となる様な事情がなくいわゆる社会に実害を及ぼす虞れがない場合には許可することができると考える。
二度目の改名が許可された裁判例
通称を名乗って生活していたことを理由に再度の改名が許可されたケース
一度、改名をした後、通称を名乗って生活をしていたことを理由に再度の改名が許可されたケースを2つ紹介します。
熊本家庭裁判所昭和38年5月25日の審判
事情は、第1章「再度の改名に関する原則的な判断基準」で、ご紹介したとおりです。
再度の改名をした方は、昭和初期~中期のこともあって、非常に広範囲に通称を名乗り続け、その証拠資料も潤沢にあったようです。具体的には私的な交友関係、ビジネス上の関係、そして現在では考えられませんが、役所や銀行等の資料もあったそうです。
そして、以下のように判断して、再度の改名を許可しました。(個人名の部分は編集しています)
通称名使用の期間が約9年余に及び、使用の幅が申立人の社会活動に伴つて広範囲であること、これに比較し先に許可を得て改名した戸籍上の名の使用の期間が約1年にすぎないことを考えるなら、むしろ通称名に改名した方が却つて社会の認識を混乱せしめないということができる。
尚本件改名の動機は姓名判断によるもので、それは法律上許される正当事由に該らないこと勿論であるが、例え改名の動機は誤つたものであつたにしても他に正当事由を充す要件を具備する以上動機について問うべきではない。
とすると本件は再度改名の必要性があり、しかも改名によつて社会に迷惑を及ぼすものでないことが、明らかであるから本件申泣は許可するのが相当であると思料する。
大阪高等裁判所平成7年6月12日の決定
これは、同じ市に同姓同名者がいて支障があったので、裁判所許可を得て改名した人が、一度名前を変更した後も、変更前の戸籍上の名前に愛着があり、これを通称として名乗り続けていたことを理由に、改名を申し立てた事例です。
家庭裁判所は、この申立てを認めませんでしたが、抗告したところ、大阪高等裁判所が以下の理由で、改名を許可しました。(具体的名前や居住地は編集しています)
- 抗告人は,A市に移転し,再びB市に戻ってきたが,同姓同名者はこれより先にC市に移転していて,現在では同人との間に前記のような混同による支障が生ずるおそれはない。
- このように,抗告人は,入社以来継続して約23年(改名後の通称使用期間だけでも約19年)以上勤務先で通称として取り扱われ,社会においても引き続きを通称として使用し,かつ,社会一般からも通称で呼ばれてきているのであるから,本名である戸籍上の名前を使用すれば却って抗告人の社会生活上の不便と周囲の混乱がもたらされることが予想できる。
- そして,一件記録を精査しても,他に本件申立てを却下すべき事情を認めるに足りる証拠は見当たらない。
僧名を理由に改名をした後、所属寺院が変わったため再度の改名が許可されたケース
これは、裁判所の許可を得て、一度僧名へ改名した後、所属寺院がかわったことから、再度、改名を申し立てた事例です。
家庭裁判所は、これを認めず、申立人が高等裁判所へ不服申立てをしたところ、以下のように判断して、改名を許可しました。(実際の名前は編集しています)
抗告人は、現にA派B院住職の地位にあり、今後も右の住職であるものと認められるところ、前記認定の事情の許では、抗告人が右寺院の住職としての社会的ないし宗教的活動を円滑に営むためには、その名を●●と改める必要があるものと解されるから、本件は、改名の正当の事由があるものというべきである。
抗告人は、先に僧籍に入つたことから改名し、更に再び改名しようとするものであるが、先の改名より既に20年近くを経ているところ、現に改名を必要とする抗告人の新たなB院住職として宗教的ないし社会的活動は、先の改名後の「▲▲」の名の許でしたA派僧侶としての宗教的、社会的活動とは、全く別個の地域及び寺院、檀徒関係におけるもので、
かつ、従前の地域及び社会関係との交渉は殆ど絶えたものであり、現に「●●」の法名が通称として行れているものであるから、更に改名することにより、特に呼称上の社会的混乱を生ぜしめる虞れがあるものとは解し難く、抗告人が先に改名したことをもつて、本件改名の正当事由を否定すべきものとはなし難く、また、抗告人が、前記説示の事由のほか、他に不当な目的で名の変更を求めるものと窺わせるところはない。
なお、僧侶や神職になったことを理由に改名をした後、僧侶・神職ではなくなり元の名前に再度改名することは、改名の典型事由としてあげられています。
私が関与した二度目の名前の変更についての高等裁判所の例
第1章「再度の改名に関する原則的な判断基準」で申し上げたとおり、二度目の改名は、原則として認められません。
認められた例
事例としては、子供の頃に両親が改名の手続きをして名前を変更していた人が、大人になってからの事情で名前を変更しようとした場合です。
以前からこういった事例は少ないながら存在しており、家庭裁判所も大人になってからの事情のみを判断して許可をしていました。ところが、二度目の改名であるので、大人になってからの事情を厳しく評価して、許可をしなかったことが起こりました。
大人になってからの事情だけで十分な理由があると考えていたので、不服申立てをしたところ、高等裁判所は「親権者が未就学児の名前を変更したことは、本人の自己の意思にもとづかないので、大人になってからの改名手続きに影響しない」として、許可しました。
この判断で重要なことは、「本人の自己の意思にもとづかない」ということです。ですので、両親が手続きをしていても、手続き時に小学校高学年~中学生であった場合は、自己の意思にもとづかないとは言いきれず、違う判断になることは十分にあり得ます。
認められなかった例
これは、変更した名前の文字が人名用漢字でかつ正字・親字であるけれども、コンピューターでは出力されない文字(例えば昔の葛飾区の葛の字等いわゆる外字)であったので、日常生活に支障をきたしていた例です。
別の文字に置き換えられてしまうため、本人確認で問題になるといった深刻な状態であっても、高等裁判所でも認められませんでした。
ですので、名前の変更を考える際には、新しい名前の漢字は慎重に選ぶ必要があり、また令和7年の戸籍法の改正の影響で振り仮名も同様に慎重になる必要があります。
このように、最初の改名時点では考えられない技術的な問題(外字や振り仮名)であっても、これが二度目の改名の許可の理由になるとは限りません。したがって、新しい名前による将来的な影響を見据えた慎重な判断が重要です。
二度目の改名の申立書に記載する際の注意点
二度目の改名を申し立てる場合は、名前を変更するための正当な事由を裏付ける強い証拠が必要なのはいうまでもありません。
この他に申立書にも、十分に注意して記載するべき内容があります。
以前、改名をした時の事情
前回、名前を変更した事情は、二度目の改名が許可されるかどうかの重要な要素になり、とても重要です。もし、証拠資料が残っていなくてもできる限り詳細に記載するべきです。
前回、改名をした後、再度の名前の変更をしなければならなくなった事情
前回改名をした後に起こったことで、名前を変更しなければならなくなった事情は、正当な事由に含まれるものです。
証拠資料があれば、これを活用して、もし証拠資料がなくても、可能な限り申立書で合理的に説明をしていくべきです。
これらの点を整理して、時系列に沿って詳細に説明することで、二度目の改名でも、事情を正確に伝えやすくなります。次の章では、この記事の内容をまとめます。
まとめ|二度目の改名
二度目の改名(再度の改名)は、法律上まったく不可能ではありませんが、家庭裁判所は原則として認めていません。社会生活上の支障や本人の生活実態など、正当な事由が明らかである場合にのみ、例外的に許可されます。
過去の裁判例では、通称を長期間にわたって使用していた場合や、宗教上・社会的な理由がある場合で、さらに社会に混乱を及ぼさないと認められるケースで許可されています。一方で、動機が軽微なものや、外字や字形の問題など技術的な理由だけでは認められにくい傾向があります。
それでも、例えば性同一障害や誹謗中傷、ストーカ被害など、差し迫った事情があれば、許可を得られる余地は十分にあります。
差し迫った事情がある場合でも、そうでなくても、前回の改名の事情と今回の事情を時系列に整理し、合理的に説明することが重要です。司法書士は、これらの事情を明確に整理し、適切な申立書を作成するお手伝いをします。
よくある質問|二度目の改名
二度目の改名は法律上可能ですか?禁止されていませんか?
戸籍法の条文に二度目の改名について規定がありませんが、裁判所は原則認めておらず、例外的に許可されることがあります。
裁判所が「原則認めない」とするのはなぜですか?
名前は社会的に個人を識別する基本情報であり、頻繁な改名は本人の同一性を不明確にし、社会生活上の混乱を招くおそれがあります。このため、裁判所は「再度の改名は原則として許されない」との立場を取っています。
ただし、合理的な理由があり社会的実害が生じないと認められる場合は、例外的に許可されることもあります。
改名を繰り返す場合、戸籍上の記録や社会的信用に影響はありますか?
改名を繰り返しても、戸籍上にはその都度名の変更が記録されます。社会的信用が自動的に下がることはありませんが、金融機関の審査に影響することがあります。
一度改名をした後、元の名前に戻すことはできますか?
一度改名した後に、元の名前に戻すことも「再度の改名」に該当し、裁判所は原則として慎重に判断しますが、例外的に許可されることがあります。なお前回の改名の事情によっては許可されない可能性が高くなります。