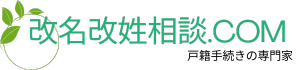改名は、裁判所の厳しい審査を経て、許可を得なければなりません。せっかく決めた新しい名前も、いくつかの特徴があると、許可をされる状況であっても、許可されないことがあります。この記事では、手続きで失敗しないために、裁判所が許可しない新しい名前の特徴を紹介します。
この記事は、2015年に公開された記事を、最近の戸籍の流れと令和7年の戸籍の振り仮名制度の開始にあわせて、書き直しています。
人の名前に使える文字:戸籍法のルールと注意点
変更後の名前は、ご自身で自由に決めることが出来ます。たとえば、変更前の名前と似た名前でなければならない、同じ文字を一部に使わなければならない、といったことはありません。
とはいうものの、新しい名前は戸籍に記録されるものなので、戸籍のルールに従った名前でなければなりません。
戸籍法では、戸籍法50条第1項 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
と定められ、常用平易な文字ついては、第2項 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
と定めています。
- 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
- 別表第二に掲げる漢字
- 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
法務省令では、ひらがなとカタカナ、常用漢字表または戸籍法施行規則の別表第二のいずれかに載っている漢字である必要があります。(常用漢字表と別表第二へリンクしていますが、リンク先が大きいデータなので、パソコンでの閲覧をおすすめします。)
また最近では、行政システムのデータ化、オンライン化のために、極力、異体字、誤字俗字ではなく、いわゆる正字・親字に文字を統一していこうという流れがあります。
この名前に使える文字の制限は、法令に定められたものですので、裁判所も戸籍法施行規則で決められた文字ではない文字が新しい名前にあると、許可をすることができません。例えば、新しい名前がローマ字表記の場合は、ローマ字の名前に変更することを許可することはできないです。(この場合、カタカナ表記で許可される可能性はあります。)
ですので、新しい名前は、「ひらがな」、「かたかな」、「人名として一般的な漢字」を使用しなければなりません。
新しい名前のヨミガナ:令和7年の戸籍法の改正
戸籍法の改正で令和7年から戸籍に、氏名のフリガナが記録されるようになります。以前は、戸籍の氏名に振り仮名の記載がなかったため、行政窓口や金融機関ごとにで振り仮名が一致しないといったことが起こりましたが、改正後は戸籍に記載された振り仮名以外は認められなくなるはずです。
改正後の戸籍法では、戸籍法13条で、
氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
、
前項第2号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
、
氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
と定めています。このため、令和7年以降は、変更後の新しい名前については、振り仮名も家庭裁判所の審査の対象になると考えられます。
ですので、前項第2号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
、氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
の二つのポイントを満たしている必要があり、新しい名前の読みを突飛なものにした場合、これを理由に名前の変更の許可がされない可能性は十分にあります。
また、改正後しばらくは、裁判所から許可されたものの、市区町村が振り仮名が条件を満たしていないことを理由に、名前の変更届を受理しないことも考えられるので、新しい名前はもちろん、振り仮名も慎重に考える必要があります。
ちなみに、名前の振り仮名だけを変更する戸籍法107条の4という規定が新設され、文字は同じまま振り仮名だけを変更する場合も裁判所の許可が必要になります。
そのほかに注意すべきポイント:裁判所の審査基準
その昔、悪魔ちゃん命名騒動という事件がありました。
裁判所は、市役所の対応の違法性を理由に、そのまま受理することを命じましたが、これに関する法務局の回答は重要です。
- 誹謗、猥褻な意味を持つ文字は認められない
- 人名の持つ概念から著しく逸脱している
- 子が将来差別を受けることが懸念され、子の利益を守る立場から、また社会通念上からも妥当ではない
- 子の福祉上、明らかに悪影響を及ぼすと思われるもの
本人が解明の手続きをする場合は、子の利益と子の福祉は対象にならないかもしれないですが、一般的な命名からかけ離れた名前の場合は、これらを理由に許可されないです。
例外的に許可される場合:具体的な事例と条件
新しい名前の文字や読みが戸籍法施行規則第60条の条件を満たさないで許可を得ることができない状況であっても、例外的に許可をえられる場合があります。
それは、通称を長年名乗っていることを理由にして、改名する場合です。通称を理由にする場合は、通称という事実を優先して、戸籍上の名前を事実に揃えるので、文字や読みに多少問題があっても許可を得ることができます。
代表的に裁判例は、昭和52年の名古屋高等裁判所、昭和53年の東京高等裁判所の判断です。
昭和52年12月の名古屋高等裁判所
昭和52年の名古屋高等裁判所では、永年使用を理由に戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の名前に変更しようとした際に、以下の三つの点をあげて、名前の変更を許可をしています。
- 永年にわたり通称名として使用していた
- 戸籍上の名前を使用すると、その人の同一性に対する認識を害し、通称名を戸籍上の名前にしたほうが、その人の認識を確実にする
- その名前に使用する文字が珍奇難解な文字でない
昭和53年11月の東京高等裁判所
昭和53年の東京高等裁判所の判断では、昭和52年の名古屋高等裁判所と同じ永年使用を理由に戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の名前に変更しようとした際に、
子の名には常用平易な文字を用いるべきものと規定する戸籍法第50条第1項の立法趣旨は、改名についての「正当事由」の有無の判断に際しても尊重されるべきものである
として、
- 長期間にわたって使用
- その通称名を正式な名前にしなければ社会生活上著しい支障をきたすような状況
- その通称名に使っている文字が、常用平易な文字から著しく逸脱していない
の三点を満たさなければ、戸籍法施行規則第60条に定められた文字以外の新しい名前への改名は、正当な理由は認められないとして許可をしませんでした。
まとめ
つまり規則第六十条に定められた文字以外の文字は使わないほうが良い
規則第六十条に定められた文字以外の文字に使用ついては、永年使用の場合であっても厳しく判断されますし、それ以外の理由では、極めて困難です。
例外と考えられるのが襲名ですが、これは襲名する伝統的な名前が重要なのであって、その名前以外の文字を変更後の名前とするのが、おかしいわけです。
永年使用を理由に名前の変更をする場合は、既に使用している通称名を使うしかありません。襲名の場合も同様です。
それ以外の理由の場合でも、既に通称名を使っているのであれば、その通称名を変更後の名前にするべきだと思います。
それ以外の理由の場合で、戸籍上の名前のみを使用している場合は、姓名判断やご家族友人に相談したうえで、ご自身が一番なじむ名前を選ぶのが、良いと思います。
よくある質問
-
改名で使える新しい名前の文字の種類は?改名後の新しい名前人の名前で使える文字でなければなりません。ですので、ひらがな、カタカナ、常用漢字、別表第二の漢字が使用可能です。
-
新しい名前の振り仮名はどのように決める?令和7年5月以降は、戸籍に振り仮名が記載されるようになるので、戸籍法等の法令で認められる範囲の振り仮名である必要があります。
参考:戸籍にフリガナが記載されます。:法務局のwebページ -
裁判所が改名を許可しない名前の特徴は?名前が誹謗中傷やわいせつな意味を持つ場合、人名として著しく逸脱した名前、常用漢字と別表第二の漢字以外の漢字を使っている場合などです。
-
ひらがな、カタカナ、常用漢字、別表第二の漢字以外の文字は絶対に許可されない?常用漢字、別表第二の漢字以外の漢字でも、通称として長年名乗っていることを理由にする場合は、許可される可能性があります。この場合でもあっても、新しい名前が人名として逸脱している場合は、許可されません。
ローマ字、。
-
令和7年5月の戸籍法改正で何が変わる戸籍の氏名に、振り仮名が記載されるようになります。
-
名前の振り仮名だけの変更も裁判所の許可が必要?令和7年5月以降は、戸籍に記録された振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。