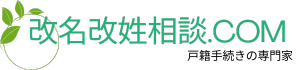近年、海外移住や外国籍の取得を選ぶ日本人が増えています。しかし、国籍喪失に関する制度は十分に知られておらず、手続きを怠ることで在留資格や住民票、国民年金、さらにはパスポートや出入国手続きにまで影響が及ぶケースがあります。
日本の国籍法では、外国籍を取得した場合、原則として日本国籍を失います。そして戸籍法では、この事実を知った日から1か月以内(国外にいる場合は3か月以内)に「国籍喪失届」を提出することが義務づけられています。
国籍喪失届を提出していない場合、戸籍上は日本人として記録が残っていても、実際には日本国籍はすでに消滅しており、日本人としての権利や義務は失われています。その結果、日本での在留資格や年金の手続きに支障をきたすほか、無効となった日本のパスポートを使用すると外国での入国審査で深刻な問題を招く可能性があります。また、戸籍が正確でないことから相続や財産手続きが滞る場合もあります。
この記事では、国籍喪失届を提出しないことで生じる具体的なデメリットを、在留資格・住民票・年金・相続・パスポートといった実務の観点から詳しく解説します。
国籍の喪失理由については、以下の記事で詳細を解説しているので、ご覧いただけるとありがたいです。
国籍喪失届とは?基礎知識
国籍喪失に関係する手続きはあまりメジャーではなく、また手続きをしたことがある人も少ないので、まずは国籍喪失の届出について簡単に解説します。
日本国籍を喪失する条件(国籍法の規定)
日本国籍は、戸籍に記載が残っていても、一定の事由に該当すれば当然に失われます。例えば、田舎の土地が江戸末期生まれの曾祖父の名義で残っていても、その曾祖父が亡くなっている事実は覆らないことと同じです。
国籍喪失の事由として代表的なものは、外国籍を自己の意思で取得した場合や、複数の国籍を持つ人が外国籍を選択した場合です(国籍法11条第1項)。
また、出生により日本と外国双方の国籍を取得した人で、一定の届出(国籍留保届)をしなかった場合(国籍法12条)、あるいは国籍選択を怠った場合なども、日本国籍を失うことがあります。
このように「日本国籍を失う」ことは、本人が日本国内の手続きをするかしないかに関係なく、法律の規定により当然に発生します。そのため、自覚のないまま国籍を喪失しているケースも少なくありません。
国籍喪失届の手続きと必要書類
日本国籍を失った場合には、戸籍法に基づき「国籍喪失届」を提出する必要があります。これは、国籍を喪失した事実を戸籍に反映させるための届出であり、いわゆる「報告的な戸籍届出」に位置付けられます。
提出者は、本人または配偶者、4親等以内の親族です。提出期限は、日本国籍を喪失した事実を知った日から1か月以内(国外居住者は3か月以内)と定められています(戸籍法103条)。
国籍喪失届書
国籍喪失届出のひな形は、お住まいの市区町村の窓口に備え付けられていることもありますが、比較的まれな手続きなので窓口にはないこともあります。
市区町村によってはホームページからダウンロードできることもあるので、お住まいの市区町村のホームページをご確認ください。(参考:国籍喪失届書のPDF(札幌市))
国籍喪失届の添付書類
国籍喪失届の添付書類としては以下のようなものがあります。
- 外国籍を取得または選択したことを証明する書類(外国の公文書)(戸籍法103条2項)
- 上記書類の日本語訳
- 提出期限を過ぎた場合の事情を説明する書面
- その他、市区町村が必要と判断する資料
外国公文書は、アポスティーユや領事認証を求められます。翻訳文については、必ずしも専門の翻訳業者によるものでなくてもよく、本人が翻訳したもので問題ありません。(参考:公印確認・アポスティーユとは(外務省))
提出期限を過ぎた事情の説明書は、仮に期限を過ぎていても必ずしも求められるものではありません。
関連条文:戸籍法103条
第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 ② 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
- 一 国籍喪失の原因及び年月日
- 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
国籍喪失届の届出の窓口と期限
国籍喪失届は、以下のいずれかの窓口に提出することができます。
- 住所地の市区町村役場
- 本籍地の市区町村役場
- 在外日本領事館
期限内に届出ることができれば、比較的スムーズに進みますが、期限を過ぎている場合や証明書を揃えられない場合には、追加の資料を求められることもあります。
特に戸籍の訂正が絡む場合は、手続き完了まで数か月単位を要することがあり、訂正後の戸籍を必要とする手続きに影響を及ぼす可能性もあります。そのため、国籍喪失を知った時点で速やかに準備を始めることが重要です。
国籍喪失届を出さないことのデメリット
国籍喪失届を出さないことのデメリットは、ほとんどの場合、日本国内の手続きに現れます。例えば、在留資格と日本国内の住民票の問題、年金制度の受給権や脱退一時金、相続手続き、戸籍訂正などの煩雑化・長期化、さまざまな支障が生じる可能性があります。
また、将来的に外国の国籍制度や現地の手続きで問題が生じる懸念があります。
日本国内での在留資格の問題
日本国籍を喪失すると、当然に「日本人としての在留資格」を失います。つまり、日本に引き続き住むためには、外国人として適切な在留資格を取得しなければなりません。
国籍喪失届を出さずに日本のパスポートで日本に出入国している場合は、形式的には不法入国・不法滞在に該当し、深刻な問題につながる可能性があります。
在留資格の例としては、日本人の配偶者や子であれば「日本人の配偶者等」といった資格を取得できることがあります。そのほか、就労や定住など、状況に応じた在留資格が必要です。いずれにせよ、日本国籍を喪失した以上、日本に住むためには外国人としての在留資格が不可欠です。
さらに、国籍喪失後は最大60日間の「経過滞在者」として滞在が認められますが、この間に在留資格を申請しなければ、形式的に不法滞在となり、退去強制の対象になるおそれがあります。そのため、国籍喪失届と在留資格申請の準備を並行して進め、戸籍に記録が反映され次第、速やかに申請することが望ましいです。
また、在留資格は日本国内の住民票とも密接に関連しています。日本人としての住民票は国籍喪失によって外国人住民票に切り替わり、または再作成されます。住民票がない状態では国民健康保険等の行政サービスの利用にも支障が出ます。したがって、国籍喪失届とあわせて在留資格の手続きの準備を進めることが重要です。
ただし、2025年時点では元日本人に対して、厳格な運用がされていません。
国籍喪失の国民年金への影響
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に加入義務がある制度です。国籍にかかわらず、日本に住所を有していれば原則として加入することになります。
また、日本国内に住所がなくなった場合でも、一定の条件を満たせば任意に加入を続けることができます(任意加入制度)。任意加入は、受給資格期間を満たすためや将来の年金額を増やすために利用されます。
ただし、この任意加入制度は日本国籍を有する者を対象としており、外国に住んでいる外国人(非日本国籍者)は原則として利用できません。したがって、海外に移住後に日本国籍を喪失した場合には、任意加入を継続することはできず、将来の年金額や受給資格に影響する可能性があります。
加入と受給の要件
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に加入義務があります。外国人であっても、適法な在留資格を持ち、住民票が作成されていれば加入の対象となります。
原則として10年以上の加入期間(保険料納付済期間や免除期間を含む)が必要です。
国籍喪失と年金の加入要件、脱退一時金の関係
外国人であっても、適法な在留資格を持ち住民票が作成されていれば、国民年金に加入することができます。加入して保険料を納め続けることで、将来老齢年金を受け取る権利が発生します。
海外在住の日本人と違い、日本を離れる外国人は、国民年金の加入の資格を喪失します。この時点で、10年以上(改正前は25年以上)日本の年金に加入している場合、老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば、その受給権は維持されます。しかし、本来はその後の納付を継続することはできません。
また、日本を離れる外国人は、国民年金を脱退する際に脱退一時金を納付期間に応じて受け取ることができます。ただし、この脱退一時金の請求は日本の住所がなくなった時から2年以内に請求する必要があります。
したがって、外国に在住している日本国籍を喪失した方は、日本国籍喪失の時期と日本を離れた時期によって、脱退一時金の請求ができないことも考えられます。
国籍喪失後の日本の年金についての具体的な対応
国籍喪失をした場合には、速やかに国籍喪失届を提出し、日本国内の手続きを整理しておくことが重要です。これによって、将来的な年金受給や脱退一時金の請求に支障が生じるのを防ぐことができます。
既に日本国籍を喪失している方で、長期間にわたって国籍喪失を届け出ていなかった方の場合、国籍喪失の時期、年金納付期間、在留資格・住民票の有無によって結論が大きく異なります。
年金事務所によれば、国籍喪失時に既発生の年金受給権は消滅しないこと、国籍喪失後の納付や脱退一時金の取り扱いについては個別の事情によって判断されるとされています。ただし、将来的に判断基準が示され、一律に処理される可能性があります。
国籍喪失届、戸籍訂正や在留資格等の手続きの準備と並行して、管轄する年金事務所に相談をすると良いでしょう。
国籍喪失後の年金事務所の管轄は、日本国内に住民票のある方は住所のある市区町村を、海外在住の方は日本国内に最後の住民票があった市区町村を管轄する年金事務所です。
国籍喪失の未届出と相続手続きにおける影響
国籍喪失届を出さずにいると、相続手続きにも大きな影響を及ぼすことがあります。
従前は、おおらかに手続きを進めることができたようですが、戸籍に日本人として記録があっても、すでに日本国籍を失っている以上、日本人として手続きを進めることは、本来であればできません。しかし、既に一部の窓口では、国籍喪失、外国人としての証明書、必要であれば戸籍の訂正を求められるようです。
ここでは、国籍喪失と相続手続きの関係について解説します。
国籍喪失者が相続人になる場合
国籍を喪失しても、相続人になれるかどうかに直接影響しません。相続人となるかどうかは、日本の民法にもとづき血縁関係や親族関係によって決まるため、国籍の有無は要件ではないからです。
しかし、日本国籍喪失者が相続人になった場合に問題になるのは、日本人としての証明書が発行されないためです。なお、日本国内に住民票がある場合は、市区町村で住民票等の証明書を取得して手続きを進められる場合もありますが、後日外国人として名義変更・訂正を求められる可能性があります。
たとえば、銀行預金・金融資産の解約・名義変更や不動産の相続登記等では、相続人の印鑑証明書等の証明書が求められますが、状況によって日本の証明書が発行されず、手続き不能になる可能性があります。
特に金融機関での本人確認が年々厳格化しており、日本国籍を喪失した人が、日本人として財産を取得したことが問題視される可能性も否定できません。
そのため、あらかじめ国籍喪失届を提出して戸籍を整理しておくことが望ましいといえます。戸籍等の身分関係の証明書が正確であれば、相続人の地位確認が容易となり、相続手続きが円滑に進められます。また後日、外国人としての名義に訂正・変更する手間も省けます。
国籍喪失者が亡くなった場合
国籍喪失者が亡くなった場合、相続手続きの準拠法は日本法ではなく原則としてその人の本国法(外国法)に従うことになります。(法の適用に関する通則法36条)つまり、誰が相続人となるか、遺産をどのように分割するかといった根本的なルールが、日本の民法ではなく外国法に基づいて判断されることになります。
したがって、外国法に基づく相続手続きが必要となり、日本で行った手続きがそのまま有効とならない場合があります。
関連条文:法の適用に関する通則法36条
(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
戸籍上の問題点
国籍喪失者が亡くなると、戸籍手続き上、大きな問題になります。
本来であれば、国籍喪失時に戸籍から除かれるので、死亡届を受理することができませんし、仮に受理されたとしてもその死亡届は無効だからです。
手続きとしては、国籍喪失の届と必要であれば戸籍訂正の手続きをしなければなりませんが、国籍喪失者の相続人が本人の国籍喪失についての証明書を取得することが困難な場合もあります。
国籍喪失の未届出と相続財産の名義変更手続き
金融機関の解約や不動産の名義変更の手続きでは、戸籍以外の証明書から日本国籍を喪失していることが判明することがあります。
このため、正しい情報を戸籍に反映させた後、外国人として相続財産の手続きを求められることがあります。
国籍喪失の届出のみの場合は、すぐに反映させることも可能ですが、戸籍を訂正する必要があるときは、訂正に時間がかかることも多く、手続きが長期化します。
また、外国籍の取得の証明書や外国の身分関係の証明書を取得することが困難であることがあり、長期化し、費用が高額になることがあります。
このようなリスクを回避するためには、あらかじめ国籍喪失届を提出し、戸籍等の証明書を整理しておくことが重要です。そうすることで、相続手続きに必要な証明書の用意がスムーズに進めやすくなります。
相続手続きを少しでも簡易にするための方法
国籍喪失者が相続人・被相続人のいずれの場合でも、日本人のみの場合と比べると証明書取得には手間がかかります。
これを回避する手段として、遺言が効果的です。遺言があることで、相続関係のための証明書を簡略化でき、手続きがスムーズになります。
また、外国の相続に関する法律は、日本の相続法と大きく異なる場合も多く、遺言がないことで長期化し、費用が高額になる可能性があります。
国籍を喪失した人、親族が外国籍の方は、ぜひ遺言を検討してください。
国籍喪失届・戸籍訂正手続きの長期化・複雑化
日本国籍を喪失した後、国籍喪失届を長期間放置していた場合、国籍喪失届の準備に時間がかかり、訂正しなければならない戸籍の記録が増えることで手続きが複雑化します。
国籍喪失届の準備の長期化
国籍喪失届の手続きには、国籍喪失の証明書が必要になります。(国籍法11条1項、2項)
国籍喪失の証明書で問題になるのは、自己の志望により外国籍を取得した場合と外国の国籍を選択した場合です。(戸籍法103条2項)
この場合は、外国の発行した外国籍を取得したことの証明書または外国籍を選択したことの証明書が、日本国籍を喪失したことの証明書になります。
しかし、日本と比較して、外国公共団体の証明書の発行に時間がかかることも多く、特に古い記録は長時間を要することも珍しくありません。
たとえば、コンピュータ普及以前に外国籍を取得している場合は、現地機関が紙の記録を検索することになり、年単位の時間を要することもあります。
また、この数十年で政変や内戦があった国や地域では、記録自体が消滅していて、その国の国籍取得の証明書の入手が困難といった事態もおこりえます。
国籍を喪失したことの証明書の状態によっては、法務局の関与が必須になり、さらに長期化を招くことになります。
戸籍訂正手続きの長期化・複雑化
長期間、国籍喪失届をせず、これ以外の婚姻届、出生届等の戸籍届出をしている場合や、コンピュータ化によって戸籍が改製されている場合は、訂正する戸籍の数と戸籍記録が増え、訂正手続きが複雑化します。
複雑化した手続きはミスを誘発する危険性があり、役所内の処理も慎重となり長期化する可能性があります。
また、戸籍訂正に法務局の関与が必要になると、さらに時間を要することがあります。
国籍喪失届・戸籍訂正手続きの長期化・複雑化の対策
手続きの長期化・複雑化の対策は、時間の経過によって、国籍喪失の証明書の入手の難易度は上がり、日本の戸籍は複雑化するので、早い段階で手続きに着手することです。
国籍喪失後に生まれた子供の日本国籍
国籍喪失後に生まれた子供は、日本の戸籍に出生届がされていても、一定の場合に日本国籍が消失します。
- 国籍喪失者と外国人配偶者の間の子供
- 国籍喪失者と日本人配偶者の子供で、日本国外で出生している
一つ目のケースでは、日本国籍喪失者と外国人配偶者の間の子供は、外国人の間の子供になるので、出生によって日本国籍を取得することがありません。
二つ目のケースでは、出生によって日本国籍を取得しますが、加えて国籍喪失者の本国の国籍や出生地の国籍を取得していると、日本国外で出生した場合は、国籍法12条が適用されます。
関連条文:国籍法12条
第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
このため、国籍留保の届出が必要になりますが、戸籍上、両親が日本人と記録されている場合は、留保の届出はされていない場合が多いため、形式上、出生時にさかのぼって日本国籍を失ったものとして扱われます。(アメリカ等出生地の国籍を取得する国では国籍留保届は受理されます。)
いずれも、国籍喪失ではなく、そもそも日本国籍を取得していなかったものとして戸籍訂正によって戸籍から消除されます。また子供が日本国内に住んでいる場合は、日本の在留資格も問題になります。
外国籍を失う可能性や外国の手続きで懸念されること
国籍喪失届を提出していない場合、日本国内だけでなく、取得した外国籍やその国や第三国での行政・生活手続きにも影響が生じる可能性があります。ここでは、特に懸念される3つの点について解説します。
外国の移民管理が厳しくなり、取得した外国籍を剥奪される可能性
2020年以降、感染症の蔓延による出入国制限や、また一部の国で移民法に関する法律の運用の厳格化進んでいます。国籍喪失届を怠り日本の国籍が残っているように振舞っていると、取得した外国籍との整合性が取れず、その国の制度上、国籍を剥奪されるリスクがあります。
とくに注意が必要なのは、その国の国籍取得後に母国の国籍の喪失、放棄手続きを努力義務として運用をしていた国では、法律の改正をせずに運用の厳格化が可能で、事前に告知されることなく処分される可能性があります。
これ以外に、その国の国籍取得後、一定期間内に国籍を選択しなければならない国もあります。この場合は、その国の法律したがってその国の国籍が消滅する可能性があります。
行政手続きや金融機関での支障
外国の役所や銀行では、国籍を証明する書類が必要になる場面が多くあります。日本の戸籍が整理されず、日本のパスポートも使用している場合、本人確認等に疑義が生じ、口座凍結や第三国での就労手続き、ビザ申請に悪影響がある可能性があります。
特に、銀行など金融機関では、マネーロンダリングやテロ資金供与防止の観点から厳格な本人確認が行われるため、無効な日本の身分証明書の利用が、犯罪関連取引の疑いをかけられ調査対象となることもあります。
無効な日本のパスポートと第三国への出入国の問題
すでに無効となった日本のパスポートを用いて第三国に入国した場合、不法入国や身分詐称とみなされ、深刻な問題を招く可能性があります。
不法な入国と見なされた場合は、長時間の拘束、入国拒否や強制送還、罰金等の処罰の対象になる可能性があります。
その事実は出入国記録に残るため、将来的な入出国やビザ申請、乗継時の滞在への悪影響があると考えられます。
国籍喪失とパスポート・出入国管理の注意点
国籍喪失届を提出していない場合、日本のパスポートや出入国管理にも影響が及びます。形式上は日本人としてのパスポートを所持していても、実際には日本国籍を失っているため、その利用は重大なトラブルを招く可能性があります。ここでは、国籍喪失後に特に注意すべきポイントを解説します。
日本のパスポートはいつ無効になるのか
日本のパスポートは、日本国籍を喪失した時点で法律上当然に効力を失います。(旅券法18条1項)戸籍に国籍喪失の事実が反映されていなくても、実体法上、日本国籍を失ったことで日本のパスポートが失効します。
国籍喪失届を提出せず、日本のパスポートを所持していても、すでに効力を失っていることに変わりはなく、使用すれば虚偽の申告や不正使用とされるおそれがあります。
さらに、国籍喪失後は日本のパスポートの更新・再発行もできなくなります。日本のパスポートは日本国籍を有することが前提であって、国籍喪失者が旅券申請をしても本来であれば受理されません。申請過程で国籍喪失の事実が判明した場合には、同時に戸籍訂正や国籍喪失届の提出を求められることもあります。
このため、日本国籍を喪失した方は、たとえ戸籍が未整理であっても、本来は、日本のパスポートを利用し続けることはできず、早期に国籍喪失届を提出し、外国籍に基づく有効な旅券を取得しておくことが必要です。
日本への入国・再入国時の注意点
国籍喪失後に日本へ入国しようとする場合、日本のパスポートを利用することは不法入国に該当する可能性があります。形式上は通過できても、後日、国籍喪失が明らかになり、滞在資格を持たない外国人とみなされることがあります。
その場合、在留資格を新たに取得しなければ日本に滞在できず、退去強制や入国禁止措置の対象になることもあり得ます。これにより、生活基盤が日本にある人でも、仕事や家族との生活に大きな支障を来すことになります。
また、国籍喪失者は、日本人として帰国することはできず、在留資格を持たなければ再入国できません。(観光等短期滞在のビザが免除されている国の方はその期間内であれば滞在できます。)日本での居住や就労を希望する場合には、国籍喪失届等戸籍の整理とあわせて、適切な在留資格を申請することが不可欠です。
なお、日本に在住している国籍喪失者であれば、入管当局も実務上は比較的柔軟に扱うことが多いですが、法律上の期限を守って、国籍喪失を届け出た後は、すみやかに日本人の配偶者や子供であることの資格(日本人の配偶者等)等でビザを申請することが望ましいです。
外国への出入国と日本のパスポート利用
第三国において無効な日本のパスポートを利用すると、不法入国や身分詐称と見なされる可能性が高く、深刻な問題を招きます。入国審査で発覚した場合は、長時間の拘束、入国拒否、強制送還、さらには罰金などの処分を受けることも考えられます。
こうした場合、領事保護はあくまで日本人を対象とする制度なので、日本の大使館や領事館に支援を求めても、国籍を喪失している以上、日本国民としての保護は受けられない場合があります。形式的に日本のパスポートを持っていても、実体法上の国籍がなければ、領事保護の対象外とされる可能性があります。
結果として、日本の在外公館が支援できず、孤立した状況に置かれるリスクも考えられます。このため、国籍喪失届を提出し、正しく身分関係を整理しておくことが極めて重要です。
国籍喪失届提出後に必要な手続き
国籍喪失届を提出した後は、日本国内に居住している場合と国外に居住している場合とで、その後の気を付けなければならない手続きが異なります。ここでは、それぞれの状況に応じた主要な手続きを整理します。
在留資格の手続き
国籍喪失届を提出すると、日本人として身分証明がされなくなるので、日本国内へ入国する場合は、外国人としての在留資格が必要になります。これまで「日本人」として居住していた方も、国籍喪失の時点で法的には在留資格を持たない状態になるため、入国管理局での手続きが不可欠です。
ただし、多くの国の方は90日以内の短期滞在であればビザを求められない国の方であれば、この期間内での入国は問題ありません。しかし、短期滞在の資格では住民票を作ることができません。
日本国内に住んでいる場合
国籍喪失届出後も日本に引き続き居住する場合には、速やかに在留資格を申請する必要があります。代表的な在留資格としては、配偶者や親が日本人である場合の「日本人の配偶者等」が考えられます。
日本国外に住んでいる場合
国籍喪失者は、外国人として日本への入国手続きに切り替わることに注意が必要です
観光や短期滞在であればビザ免除制度を利用できる国籍の場合もありますが、日本での居住や就労を希望するのであれば、事前に取得できる在留資格を確認して、在外公館でビザを申請する必要があります。
在留資格の対応
いずれの場合も、国籍喪失届を提出した直後は手続きが煩雑になりやすいため、早めに入管や在外公館に相談しておくことが望ましいでしょう。
なお、ビザ申請などの入管の手続きは行政書士業務であるため、必要に応じて専門の行政書士に相談を検討するとよいでしょう。当事務所では在留資格の取得や変更手続きそのものはお引き受けできません。ただし、国籍喪失届や戸籍の整理といった関連する手続きについては司法書士が対応できますので、併せてご相談いただけます。
また、日本国籍喪失後も日本に永住し続けるのであれば、将来的に永住資格の申請や簡易的な帰化手続きも検討するべきです。
年金への影響
国籍喪失届を提出すると、日本国籍を前提にしていた国民年金や厚生年金の取扱いに影響が生じます。もっとも、国籍喪失そのものによって直ちに年金の受給権が失われるわけではありませんが、今後の加入や手続きについては注意が必要です。
日本国内に住んでいる場合
国籍を喪失しても、日本国内に住所があり在留資格を有していれば、外国人住民として引き続き国民年金に加入することができます。厚生年金についても、日本国内で雇用されていれば原則として加入対象となります。
ただし、国籍喪失の事実を届け出ないまま手続きを続けると、記録上の不整合が生じ、将来的に受給申請時に確認作業や追加書類が必要になることがあります。そのため、事前に記録を整理しておくことが望ましいでしょう。
日本国外に住んでいる場合
海外に居住する日本人は任意で国民年金に加入することができますが、国籍喪失後はこの制度を利用することはできません。したがって、国外に住んでいる国籍喪失者は新たに国民年金を納付することはできなくなります。
問題になるのは、国籍喪失後または日本国外転出後の年金の取り扱いです。外国人が日本国外に転出して年金の加入資格を失ったときは、納付済み保険料の一部払い戻しを請求することができます(脱退一時金の請求)。ただし、この請求は年金加入資格を喪失してから2年以内にしなければなりません。
年金制度の被保険者の資格を喪失した日とは、外国籍を取得した時点で日本に住民票がなかった方は取得時、日本に住民票があった方は国外転出時です。
2025年時点で年金事務所に確認したところ、基本的には次の2点が明確になっています。
- 国籍喪失時までに発生していた年金受給権は消滅しない
- 国籍喪失後の対応は、個別に年金事務所と相談
しかし、今後統一的な対応が決まるかもしれず、早いうちに対応しておくべきです。したがって、国籍喪失の届出の準備とあわせて、年金の手続きも年金事務所に相談するべきです。なお、年金事務所の管轄は、日本で最後に住所のあった市区町村を管轄する年金事務所です。
住民票・健康保険の手続き
国籍喪失届を提出すると、日本国内に住んでいる場合は住民票や健康保険の扱いが変わります。これまで日本人として登録されていた住民票は、日本国籍の喪失後は外国人住民としての住民票に切り替える必要があります。
なお、外国に転出を届出済みの方は住民票・健康保険の手続きは関係ありませんが、日本国内に住民票をおいている場合は在留資格が求められます。
しかし、国籍喪失届出後、在留資格を取得するまでは、あくまで短期滞在の資格ですので、すみやかにビザの申請をして、正規の在留資格を取得し、住民票等の切り替え手続きをしなければなりません。
住民票の切り替え
市区町村役場に国籍喪失の事実を届け出ることで、住民基本台帳上の国籍欄が修正され、外国人住民として住民票が作成されます。これにより、従来どおり住民票を利用して各種行政サービスを受けることができます。
- 氏名がローマ字表記に
- 国籍・地域
- 在留資格と期間
- 在留カード番号
- 資格外活動許可の有無
なお、外国人住民票の通称として、国籍喪失前の戸籍に記録されていた漢字の氏名を記録できる場合があり、住民票の切り替え時に市区町村の窓口で相談してください。住民票に通称として漢字の氏名が記録されている場合は、職場や公的手続、銀行口座等を漢字の氏名で保持できます。
健康保険の手続き
日本に住所があり、在留資格を有していれば、国籍喪失後も国民健康保険や被用者保険に加入し続けることができます。会社員であれば勤務先を通じて、個人事業主や無職の場合は市区町村役場で国民健康保険の切り替え手続きが必要です。
ただし、在留資格を失うと健康保険の資格も失われるため注意が必要です。
その他の行政サービスとの関係
住民票や健康保険の切り替えを行うことで、児童手当や各種税務手続きなど、他の行政サービスも継続して利用できます。逆に、切り替えを怠ると、住民票の記録との不一致により不利益を受ける可能性があります。
このため、国籍喪失届を提出した後は、すみやかに市区町村役場で住民票と健康保険の手続きを済ませておくと同時にその他の行政手続きを確認することが望ましいでしょう。
金融機関・財産に関する手続き
国籍喪失届を提出すると、銀行口座や証券口座、不動産登記など、日本国内にある財産の取扱いにも影響が出る可能性があります。国籍や在留資格の変更は金融機関や行政手続きに直結するため、早めの対応が必要です。
銀行口座・証券口座の手続き
銀行や証券会社では、本人確認のために国籍や在留資格の情報を確認されることがあります。国籍喪失後は、日本国籍ではなく外国籍としての登録に切り替える必要があり、追加の書類提出を求められる場合があります。
特に、マネーロンダリング防止や外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)などの国際的な規制により、居住地や国籍に変更があった場合は申告を怠ると口座が利用停止になる可能性もあります。国籍喪失届を提出した後は、速やかに取引先金融機関に連絡し、登録内容を更新してください。
不動産登記の名義変更手続き
国籍喪失後も日本国内の不動産の所有権は維持されます。ただし、登記簿上の氏名等を変更または訂正する必要が生じることがあり、この手続きは「登記名義人の表示変更」にあたります。法務局での登記変更手続きには、氏名等の変更や訂正の理由を証明する資料が必要です。
登記情報と住所氏名が一致しないままにしておくと、不動産売買や担保設定の際に手続きが滞る可能性があります。スムーズな取引を行うためにも、早めに修正しておくことが重要です。特に訂正の登記申請(更正登記)を申請しなければならない場合は、必要書類が複雑化することが多いため、専門家への相談が望ましいでしょう。
また、日本国外に在住している場合は、日本国内の連絡先も登記事項として申請書の記載する必要があります。
- その登記申請以前に日本国籍を喪失していた場合→住所氏名等の訂正(更正)登記申請
- その登記申請後に日本国籍を喪失した場合→住所氏名等の変更登記申請
なお、2026年4月より、住所氏名の変更の登記申請が義務化され、最大5万円の過料が科される可能性があります。
その他の財産に関する手続き
生命保険や年金基金等の財産についても国籍や居住地の変更を届け出る必要があります。特に海外在住の場合は、非居住者としての取扱いに切り替わり、給付に影響が出たり、失効する場合もあります。
これらの財産に関する手続きは、それぞれの機関や契約内容によって異なるため、国籍喪失届を提出した時点で早めに関係機関へ相談しておくことが望ましいでしょう。
よくある質問|国籍喪失届を出さないことのデメリット
国籍喪失届とは何ですか?提出が必要な人や提出期限、根拠法令はどうなっていますか?
国籍喪失届は、日本国籍を喪失した事実を戸籍に反映させるための戸籍届出です。本人または配偶者・4親等以内の親族が、「日本国籍の喪失を知った日から1か月以内」(国外にいる場合は3か月以内)に、届け出なければなりません。戸籍法103条に根拠があります。 詳しくは 「国籍喪失届の基礎知識」 で解説しています。
外国籍を取得した場合、日本国籍はいつ失われ、二重国籍のまま残ることはありますか?
自ら外国籍を取得した場合、その時点で日本国籍は当然に失われます。二重国籍のまま存続することはありません。 詳しくは 「日本国籍を失う条件」 で解説しています。
国籍喪失と国籍離脱の違いは何ですか?
国籍喪失は、すでに「日本国籍を当然に失った」ことを届け出る報告的な届出です。一方、国籍離脱は、二重国籍状態の方が、自らの意思で日本国籍から離脱する手続きです。
ただし、戸籍届書の用紙は同じものを使います。詳しくは 「喪失と離脱の違い」 で解説しています。
国籍喪失届を出さない場合、日本国籍や戸籍はどう扱われますか?
日本国籍はすでに失われていますが、戸籍はそのまま残ります。その結果、日本人としての証明書を取得できてしまい、後日大きな問題になることがあります。
なお、日本の公的機関が日本国籍を喪失した事実を把握した場合、本籍地の市区町村にこの事実を報告することになっています(戸籍法105条)
詳しくは 「国籍喪失届を出さない場合の影響」 で解説しています。
国籍喪失届はどこに提出しますか?市区町村役場、大使館・領事館のどちらでも可能ですか?
国内では本籍地または住所地の市区町村役場、国外では在外公館(大使館・領事館)に提出できます。 詳しくは 「届出の窓口と期限」 で解説しています。
国籍喪失届のための必要書類は何ですか?
外国籍を取得したことを証明する外国公文書とその日本語訳、戸籍謄本などが求められます。外国公文書にはアポスティーユや領事認証が必要です。 詳しくは 「必要書類の一覧」 で解説しています。
国籍喪失届の審査や反映にどのくらいの期間がかかりますか?戸籍にはどのように記載されますか?
通常は数週間、場合により半年以上かかります。戸籍には喪失日・事由・届出日が記録されます。 詳しくは 「審査期間と戸籍への記録」 で解説しています。
国籍喪失届を出さない場合、パスポートや出入国にどんな影響がありますか?
戸籍の届出をしなくても、日本のパスポートは失効し、使用すれば不法入国や身分詐称に該当する可能性があります。不法滞在状態となるリスクがあります。(旅券法18条1項)
詳しくは 「パスポート・出入国の影響」 で解説しています。
国籍喪失届を出さない場合、住民票や健康保険、年金に影響はありますか?
住民票は外国人住民票へ切り替えが本来必要で、国籍喪失を届け出ないと記録の不整合が生じます。また、日本国外に居住している場合、年金に関する権利が失われる可能性があります。 詳しくは 「住民票・保険・年金への影響」 で解説しています。
国籍喪失後、日本のパスポートや出入国はどう扱われ、再入国や短期滞在はどのようにできますか?
本来的には日本のパスポートは使えません。外国籍者として、国籍取得国の旅券で入国・再入国や中長期ビザ又は身分系ビザの申請を行う必要があります。詳しくは 「再入国・短期滞在の取扱い」 で解説しています。
住民票は外国人住民票に切り替わりますか?記載事項や通称の扱いはどう変わりますか?
国籍喪失届後、住民票は外国人住民票に切り替わり、国籍・在留資格等が記載されます。通称として日本の戸籍に記録されていた漢字の氏名を登録できる場合もあります。 詳しくは 「外国人住民票への切り替え」 で解説しています。
国籍喪失後、健康保険(国保・社保)は継続できますか?在留資格との関係はありますか?
国民健康保険であれば、在留資格を有していれば継続可能です。社保の場合は、就労可能な在留資格である必要があります。したがって、すみやかに在留資格を整える必要があります。 詳しくは 「健康保険継続と在留資格」 で解説しています。
国籍喪失は子どもの手続きにはどのような影響がありますか?
国籍喪失後に生まれた子供は、条件によっては日本国籍を取得できない、または生まれた時にさかのぼって失う場合があります。戸籍訂正、在留資格の申請等が必要となる場合もあるため注意が必要です。 詳しくは 「子どもの国籍と手続き」 で解説しています。