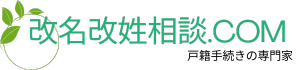「結合姓にしたいけれど、日本ではできるの?」「どんな手続きが必要?」──国際結婚をした、あるいはこれから考えている方の間で、氏に関するこうした疑問はとてもよく聞かれます。日本の戸籍制度では、婚姻後、結合姓(複合姓・ダブルネーム)に戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。本記事では、結合姓の概念、日本で認められる条件、同じ戸籍にいる子供への影響を明確にし、現実的な手続きや対応について、今後の判断に役立つ情報をまとめました。
結合姓、複合姓、ダブルネームとは?

国際結婚を機に、夫婦の氏をどのようにするかは、多くの方にとって悩ましい問題です。国ごとに結婚と氏に関する扱いがちがい、「結合姓」「複合姓」「ダブルネーム」等の言葉を聞いても、意味や違いがよく分からないという声も少なくありません。
いろいろな国の婚姻と氏の制度
日本では婚姻時に夫又は妻の氏を選択することができます。どちらかの氏以外の氏をえらべないことになっています。日本以外の国では、文化的・宗教的・言語的な理由から様々な婚姻後の氏の取り扱いがあります。
例えば、日本に近い中国、韓国、台湾では、原則婚姻は当事者の氏に影響を与えません。例外として冠姓という制度があって婚姻相手の氏を自分の氏の前につけることができますが、手続きが複雑になるので、今ではあまり使われることがないようです。
興味深いところであれば、原則氏の変動はなく、例外で妻が夫のフルネームを自身の氏にすることができる制度などもあります。
過去を見ると、婚姻で当事者の氏が変わらない/妻が夫の氏になっていた国が多いように感じます。20世紀から現代にかけて、妻が婚姻前の氏又は結合姓を選択できる国が増えている傾向があります。
結合姓、複合姓、ダブルネーム、結合氏?どれが公的な呼び方なのか?
結合姓は、compound nameと英語で書きます。compoundは日本語で「合成の」「複合の」といった意味があります。これを結合姓、複合姓と日本語に翻訳するようになりました。別の単語ですが、日本語ではどちらも同じものです。裁判所では結合氏を使うことが多いと思いますが、これも同じものです。
実は“ダブルネーム”は法律用語とはいえません。ダブルネームは少なくとも氏について言う場合は誤用だと言えます。英語ですとdouble nameだと思いますが、氏に関して使うものではなさそうです。
日本では、戸籍上で結合姓、複合姓を使うことは、今のところ認められていません。戸籍のシステム上では氏の部分に記号やスペースを入れることができない仕様になっています。明治維新で新しく氏を作る時に結合姓や地名+苗字といったものがあったそうですが、現在ではあまり見かけなくなっています。ちなみにこの氏の場合は、「氏+氏」ではなく一つのつながった氏として記録されています。
| 用語 | 説明内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 結合姓/複合姓/結合氏 | 婚姻で夫婦それぞれの姓を合成したもの。法律的な文脈でも使われている。 | 裁判例では「結合氏」を使用している。 |
| ダブルネーム | 結合姓、複合姓等と同義で使われていますが、正式な呼び方ではなさそうです。 | goo辞書 |
日本人でも結合姓にすることはできるのか?
日本人同士の場合は、現在の民法では夫又は妻の氏を選ぶことになるので、結合姓にすることはできないことになっています。(民法750条)
国際結婚をした日本人の場合、原則、結婚によって氏は変わりませんが戸籍法107条4項の届出や裁判所の許可を得て氏を変更することができます。
この時に外国人である配偶者の本国の制度・法律で結合姓が認められているときは、裁判所の許可を得て日本人の戸籍上の氏を結合氏にすることができます。
一方で、日系外国人と日本人の婚姻の場合は注意が必要です。相手の氏が日本由来の氏で、結合姓が日本の氏+日本由来の氏となる場合は、裁判所の判断が分かれそうです。なぜならば、日本人同士でも結合姓にできると誤解を与えたり、奇妙な氏と考えられ、一般的な不許可の理由に該当する可能性があります。
先にも説明したように、日本の戸籍では「氏+氏」ではなく、「一つのつながった氏」と記録されて、区切り文字やスペースを入れることができませんが、パスポートでは事情を説明して、スペースを入れることができます。
子供の氏にも影響があるのか?

「結合姓に変えたら、子供の氏も変わるの?」こうした不安を感じる方も少なくありません。
日本の戸籍の氏を結合姓にするためには、必ず裁判所の許可を得て届け出る必要があります。似ている制度で婚姻から6か月以内に外国人配偶者の氏へ変更する手続き(戸籍法107条4項)の場合は、結婚した本人以外の氏に影響を及ぼしません。
しかし、結合姓にするための手続きでは、同じ戸籍にいる人全員に氏が変わります。
特に未成年の子供が同じ戸籍にいる場合、氏の変更がどのような影響を及ぼすのかは重要な関心事です。ここでは子供の氏がどう扱われるのかを、場合分けしながら説明します。
同じ戸籍に未成年の子供がいる場合
まず同じ戸籍に未成年の子供がいる場合です。
未成年者は原則親と同じ戸籍にいることになり、日本人親が結合姓になれば、子供も同じ結合姓になります。
もし、子供が外国籍も持っているときは少し注意が必要です。子供の外国のパスポートの氏と日本の戸籍の氏が一致しないことがトラブルになることがあります。
同じ戸籍に成人した子供がいる場合
子供が成人しているときは、選択肢があります。
未成年の場合と同様に、日本人親と同じ戸籍に残り、親と同じ結合姓を名乗ることができます。
子供が戸籍の氏をそのまま名乗りたい場合は、分籍の手続きで、本人単独の新しい戸籍を作り、元の氏のままでいることもできます。
| 未成年の子供 | 成人した子供 | |
|---|---|---|
| 結合姓/複合姓/結合氏 | 〇:選択可能 | 〇:選択可能 |
| 元の氏 | ×:選択不可 | 〇:選択可能 |
親子の氏が分かれる国のケースでは?
外国人配偶者の本国法で親子の氏が一致しないことがある国もいくつかあります。
日本の戸籍の問題に限っていうと、前述のとおり原則日本人親の戸籍上の氏になります。
子供の氏が一致しないことで不便なことが起きるようであれば、結合姓へ氏を変更する前に分籍の手続きや外国人親の氏への変更の手続き(戸籍法107条4項)等で子供の氏を調整することもできます。
戸籍の氏を結合姓にしたいときは?

これまで見てきたとおり、日本の戸籍の氏を結合姓にするためには、一定の条件と手続きを経る必要があります。
実際に「結合姓にしたい」と思ったとき、最初のハードルとなるのが家庭裁判所の許可です。
ただし、外国人配偶者の本国に結合姓の制度がある場合でも、日本で必ず氏の変更が認められるわけではありません。
ここでは、許可を得るために必要な条件や申立ての流れ、必要な書類について、制度的観点から整理して解説します。
結合姓に変更するための「やむを得ない事由」
結合姓に氏を変更することも、氏の変更ですので、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。
結合姓に変更する場合の『やむを得ない事由』は、一般的な氏の変更とは異なる運用がされる傾向があります。
配偶者の本国法で結合姓が法律的に認められていること
配偶者の本国法で結合姓が認められていることは、必須の条件です。
結合姓がない国の配偶者で、これ以外の事情を集めていっても、裁判所の許可を得ることはまず認められることはないと考えられます。
結合姓への変更の必要性が認められること
担当の裁判官によって違いがありますが、変更する必要性というのもポイントです。しかし、一般的な氏の変更と比べると比較的柔軟に判断される傾向があります。
過去に扱った例で、許可された例をあげます。
- 日本国外に住んでいる方で、日本のパスポートとその国のビザは日本の氏、外国の婚姻証明書や住民登録等の書類は結合姓になっているようなケース
- 結婚の法律的な効果で、妻の氏が自動的に結合姓になる国の人と結婚したケース
- 結婚後、通称として結合姓を名乗っているケース
最後の通称として結合氏を名乗っている場合は、婚姻期間や結合氏を名乗っている証拠資料が裁判所の判断に影響します。通称の永年使用を理由にする氏の変更よりは難しくありません。
結合姓が認められた裁判例を紹介
東京家庭裁判所平成2年と6年、神戸家庭裁判所の平成6年の許可の例が、過去の判例誌に掲載されています。
平成2年6月の東京家庭裁判所の裁判例
海外で婚姻し現地の公的書類に結合姓で登録されていた人が、日本に帰国後、戸籍の氏との不一致により生活上の支障が生じたため、結合姓への変更を申し立てたときの家庭裁判所の判断です。
申立人についてはその氏を結合姓へと変更する必要性が高いといえるが、戸籍法は(中略)、本件のように夫婦の双方の氏を併記した氏への変更については何ら規定していない(後略)。
国際結婚も増加している社会情勢のもとにおいては単に外国人配偶者の氏の変更するのでは足らず、本件のように妻の氏と夫の氏を併記した新たな氏に必要性が高い場合が出てくることは当然と考えられる。そして、このような事情は十分考慮に値し、一方、このような氏の変更が認められても我が国の氏の制度上特に支障があるとは思われない。
このように裁判所は判断して、結合姓への変更を許可しました。
平成6年1月の神戸家庭裁判所の裁判例
平成6年1月の神戸家庭裁判所の裁判例は、婚姻した後、結合姓を通称氏として名乗っている人が、結合姓にするために申立てた事例です。
神戸家庭裁判所も、平成2年の東京家庭裁判所と同じように判断して、許可しています。
東京家庭裁判所との事情の違いをまとめると、以下のようになります。
| 平成2年の東京家庭裁判所 | 平成6年の神戸家庭裁判所 | |
|---|---|---|
| 結合姓の制度の有無 | あり | あり |
| 公的証明書の有無 | 外国の公的証明書に記録あり | なし |
| 通称の使用状況 | あり(外国で) | あり |
| 日常生活での不便 | あり | あり |
このように、必ずしも公的書類は必須ではなく、「通称の使用」・「日常生活での不便」がポイントになっています。
平成6年10月の東京家庭裁判所の裁判例
平成6年10月の東京家庭裁判所の裁判例も上の二つと同じ判断基準「通称の使用」・「日常生活での不便」の2つをあげて、許可しています。
事情は平成2年6月のものと同様ですが、配偶者と氏が違うという理由で第三国の配偶者ビザが拒否され、渡航を断念せざるを得ず、大きな不都合が発生していました。
実際には、ここまで大きな不都合が必要とはいえませんが、「日常生活での不便」は重要です。
裁判例の補足
うえの裁判例はどれも、結婚直後(1~2年以内)で通称を名乗っている期間も半年から1年程度でした。
通称を名乗っている期間が短くても必ず許可されるわけではなく、結婚期間と通称の期間のバランス、例えば結婚後30年で通称の期間が半年といった場合は、許可されない傾向があります。
婚姻期間、通称を名乗っている期間、日常生活での不便の大きさ等の状況によって、結果が異なる可能性があるので、手続きにあたって、具体的な状況を踏まえた準備が重要です。
氏の変更許可の手続きの流れと必要書類
結合姓への変更は、裁判所で許可を得ることが第一歩です。
裁判所の手続きでは、証拠資料を整えたうえで、手続きを進める必要があります。この章では、申立の準備、申立書、裁判所の許可、その後の氏の変更届出までの流れを、実務的な観点から整理してご説明します。
手続きを検討している方は、ご自身の状況を確認しながら、必要な書類等を事前にチェックしておくことで、スムーズに進められます。
1.現在の状況の確認
まずは、現状をチェックすることがとても大切です。以下の3つのポイントを確認しましょう。
- 配偶者の本国に結合姓の制度があるか?
- 通称として結合姓を名乗っているか?
- 日常生活に不都合はあるか?
1つ目の配偶者の本国の制度は必須条件です。配偶者に聞いてみるのも良いですが、現地の役所のホームページで確認することで確かな情報を得ることができます。
2つ目の通称で結合姓を使っていることは、ご本人が一番よく知っていると思います。
3つ目の日常生活の不都合は、大きな不都合、小さな不都合、どんな些細なことでも、あとから役立つ可能性があるため、気になった点はすべて書き出してみましょう。
2.申し立てに必要な資料の準備
2.現状の確認が終わったら、申立のための証拠資料の準備をしましょう。
チェックポイントごとに用意する資料の例を挙げていきます。
本国に結合姓の制度があることの資料
国に結合姓の制度があることを証明する必要があります。最良の資料は、本国の法律の条文です。
法律上婚姻時の氏の規定がなく、同姓・別姓・結合姓だけではなく新しい姓も無制限に選択できる国や、慣習で婚姻時の氏がきまる国では、条文がないこともあります。
こういった場合は、現地の役所等の窓口のホームページや婚姻届のひな形・記載例、現地の法律の解説書、または婚姻証明書といったものが代替の資料になります。
これらの資料は、現地の公用語で書かれているので和訳文を用意しなければなりません。
通称として名乗っていることの資料
通称として名乗っていることの資料は、公文書である必要はありません。日常生活で使っているものも資料になりえます。
日本国外の在住の方でしたら、ビザは日本のパスポートの氏名と同じだと思いますが、現地の住民登録の証明書や身分証明書、銀行等の書類、携帯電話の明細等は結合姓で発行できることがあります。
配偶者の本国の婚姻証明書の本人の氏が、結合姓になっていることもよくあります。
郵便物・メールやメッセージアプリのやり取りも資料になりえます。
結婚からあまり時間が経っていなければ、かならずしも多数の資料をそろえる必要はありませんが、できれば異なる資料が複数あると安心です。
- 外国の身分証明書等の公文書
- 郵便物や宅配便等の伝票
- メールやメッセージアプリのやり取り
- 表彰状や感謝状
- 参加したイベントの招待状や案内状、告知の印刷物、記念品
- メッセージカード
日常生活の不都合の資料
日常生活の不都合については、結合姓への氏の変更の場合であれば、他の理由での氏の変更と比べて、最近の裁判所は厳格に証明を求めていないと考えています。
さしせまった具体的で重大な不都合ではなく、将来起こりうるもの、漠然とした不安、日常的におこる不便程度でも十分です。
もちろん、すでに発生している重大な不都合を証明できる資料があれば、それを裁判所に提出するべきです。しかし、そうでなければ無理に資料を用意せず、申立書に記載しましょう。
ですので、日常生活の不都合については、資料がないからといってあきらめず、申立書で状況をわかりやすく丁寧に説明すれば、問題ありません。
その他の添付書類
申立書には、現在の戸籍を添付する必要があるので、忘れずに取得しましょう。
日本に住民票がない人は、日本国内での最後の住所を証明する必要があるので、「戸籍の附票」も用意しなければなりません。
また、もし15歳以上のお子様が現在の戸籍に記録されているときは、お子様の同意書もあると手続きがスムーズになります。
3.申立書の作成
準備が整ったら、申立書の作成を始めましょう。
申立書のひな形は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできますし、家庭裁判所の窓口に備え付けてあります。
申立書の1ページ目の記入
申立書の1ページ目は、本籍、氏名、住所、連絡先等あなたの情報を記入するページです。準備した戸籍や附票を参照して、間違えないようにしましょう。
結合姓にする場合の申立書の2ページ目の「申立ての趣旨」
申立ての趣旨の欄は、裁判所に何を許可して欲しいかを明確に記入する必要があります。
裁判所のひな形を使うのであれば、「申立人の氏(今の氏)を(結合姓)と、氏の振り仮名(今の氏のヨミガナ)を(結合姓のヨミガナ)と、それぞれ変更することの許可を求める。」と記入すれば問題ありません。
注意点は、以下の二つです。
- 変更後の結合姓のうち、配偶者の氏の部分は、原則、戸籍に記録された配偶者氏名の氏以外は認められません。
- 配偶者が元から結合姓の場合は、相手方の国の制度にのっとって対応しなければなりません。
1つ目:例えば戸籍に配偶者の氏が「デービス」と記録されている場合は、申立の趣旨の変更後の氏を「自分の氏+デイヴィス」とすることはできません。「ウイリアムズ」を「自分の氏+ウィリアムズ」とするのは許可される可能性があります。
2つ目:例えば、スペイン、ポルトガルの文化でしたら「相手の父方の氏+自分の父方の氏(自分の父の氏+相手の父の氏)」になります。結合姓の人の配偶者が、さらに氏をつなげて「結合姓+自分の氏」とすることができない国もあります。
余談ですが、相手の父方の氏+自分の父方の氏を結合する国の場合、日本人の氏が両親の離婚等で母の氏になっているときはどうなるか?という疑問が生じます。理論上は3とおりの対応がありますが、実務上は気にせず手続きをしても大きな問題にはなりません。
結合姓にする場合の申立書の2ページ目の「申立ての理由」
申立ての理由の欄は、なぜ、結合姓に変更しなければならないのかを、裁判所に説明するとても重要な部分です。
申立書のひな形を見ると典型的な理由が1~8まで例示されていて、9番目にその他の理由となっています。結合姓に変更する場合は、「外国人配偶者の氏へ変更したい」にあてはまりそうですが、「9.その他(以下のとおりです)」とするのが間違いないです。
申立ての理由のポイントは、以下の4つです。
- いつ、どの国の国籍の人と婚姻したか
- 配偶者の本国の婚姻制度に結合姓の制度があること
- 結合姓をいつごろから通称氏として名乗っているか/名乗ったことはないのか
- 結合姓と戸籍の氏が一致しないことで起こる日常生活の不利益
1つ目:結合姓を選択できるかの最初のポイントが、配偶者の国籍です。戸籍の配偶者欄の「配偶者の国籍」の記載で証明しますが、配偶者が複数の国籍を保有している場合はすべて書きましょう。
2つ目:ここでは、配偶者の本国に結合姓の制度があることを具体的に説明します。自分の氏+相手の氏、または相手の氏+自分の氏の順番なのか、それとも順番に決まりがないのかを説明します。準備をした相手方の国の資料で証明をしなければなりません。配偶者が複数の国籍を有している場合は、制度の証明が少し複雑になるので、専門家に相談をすることをお勧めします。
3つ目:いつごろから、結合姓を通称として名乗っているかも重要なポイントです。準備した通称の資料で証明しましょう。名乗っていないことはマイナスの要素です。準備期間中に名乗り始めて資料を集めるのも良いでしょう。
4つ目:日常生活の不利益は、状況をわかりやすく丁寧に説明すれば問題ありません。証拠資料があるものは、積極的に裁判所に開示するべきです。簡単に想像できる不利益は、資料がなくても説明するべきです。
4.裁判所へ申し立て、その後の手続き
申立書が出来上がったら、申立書と用意した添付書類・資料の1式を裁判所に提出しましょう。この時に手数料として、収入印紙800円と郵便切手1,500円~2,500円程度を一緒に提出しなければなりません。
裁判所へ直接持ち込むことも、郵送ですることもできます。郵送する場合は書留郵便やレターパックを利用するのが安心です。
裁判所から連絡があったら、きちんと対応してください。無視をしたり、放置すると却下されます。
許可を得た後は、その後の手続案内の書類を渡されると思います。それに従って、確定証明書を取得して、市区町村への氏の変更届を届け出れば、戸籍の氏が正式に結合姓に変更されます。
許可をされなかった場合
裁判所が許可をしない理由として、以下のものが考えられます。
- 配偶者の本国に結合姓の制度がない
- 結合姓の制度が証明されていない
- 通称氏と日常生活の不利益が、氏を変更しなければならないとは言い切れない
- 申立てを許可できない事情が本人にある
配偶者の本国に結合姓の制度がない場合は論外ですが、あってもきちんと制度を証明できない場合は許可されません。証明が不足しているときは、裁判所から追加の資料を求められるので、しっかり対応すれば大丈夫です。
不都合の程度や通称を名乗っていることの期間・資料の量が不十分であることも、許可されない要素になります。こういった場合は、申立てを一度取り下げて、通称の資料を整えてから再度申立てをするか、事情が大きく変わった時(例えば配偶者の本国に移住する等)に改めて申し立てるのが良いでしょう。
申立てを許可できない事情が本人にあるというのは、氏を変更する目的が、例えば犯罪歴・破産歴の隠ぺいなど不当な目的である場合や、頻繁に氏や名前を変えているような場合です。ただ結婚が原因での氏の変更であるので、絶対に許可されないわけではありません。
許可をされなかったとしても、許可されなかった理由を分析して、足りない部分を補えば許可をされる可能性は十分にあります。
結合姓(複合姓・ダブルネーム)を考える国際結婚夫婦へ-日本の制度と手続きのポイントを解説のまとめ

「結合姓にできるの?」「手続きは複雑?」「外国の制度まで調べなければならないの?」──国際結婚をきっかけに、こうした疑問や不安を抱える方は少なくありません。
結合姓への変更は、配偶者の本国の制度を理解し、必要な資料を整えるところから始まります。そのうえで、通称の使用状況や生活上の支障を丁寧に説明することが、家庭裁判所の判断に大きく影響します。
最初は難しく感じるかもしれませんが、一つひとつ段階を踏んで準備をすれば、前に進むことは十分できます。この記事が、その最初の一歩となり、皆さまの手続きに少しでも役立てば幸いです。
ご自身の状況に合った進め方に不安がある方は、専門家へのご相談をおすすめします。当事務所では、国際結婚に関わる氏の変更に関して、国内外からご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。
問い合わせてみる結合姓(複合姓・ダブルネーム)への変更についてよくある質問
-
結合姓にするために、なぜ裁判所の許可が必要なのですか?日本人同士の婚姻では、結合姓を使えないのでしょうか?日本の戸籍制度に結合姓がなく、外国人配偶者の氏への変更届(戸籍法107条2項)では、戸籍に記録されている配偶者の氏にしか変更できません。しかし、結合姓に変更することのニーズもあるので、裁判所のチェックを経て結合姓への変更が認められるようになりました。
日本人同士は、戸籍に結合姓の制度がないので、認められません。 -
配偶者の国では結合姓が一般的ですが、それだけで、日本で結合姓への変更が許可されるのでしょうか?配偶者の国に結合姓の制度があることは証明する必要があります。またこれだけではなく、結合姓に変更しなければならない必要性も求められます。
-
日本に住民票がありません。それでも結合姓への変更手続きはできますか?日本に住民票がなくても、最後に日本の住所があった地域を管轄する家庭裁判所で手続きをすることができます。氏の変更届は本籍地の市区町村又は領事館に届け出ることができます。
参考記事:外国在住の日本人が、日本の家庭裁判所で改名・改姓の手続をする方法 -
外国語の書類があります。翻訳は必要ですか?自分で翻訳してもいいんでしょうか?日本の裁判官・職員さんは、外国語がわからない設定なので、日本語に翻訳をした文章を添付する必要があります。ご本人や配偶者の方が翻訳しても問題ありませんが、末尾に「正しく翻訳しました」といった追記をして、署名(押印)をしなければなりません。外国語の資料が外国公文書であっても、公印認証・アポスティーユを求められることは、ほとんどありません。
-
結合姓って戸籍にどう記載されますか?スペースやカタカナは使えますか?戸籍の氏の部分には、記号やスペースを使用することができません。自分の漢字の氏と配偶者のカタカナの氏がつながって記録されます。(例:〇「田中スミス」、×「田中 スミス」、×「田中=スミス」等)パスポート記載されるローマ字表記の氏名は事情を説明して、氏と氏の間にスペースを入れることができます。
-
結合姓に変えたら、子供の氏も一緒に変わるんですか?結合姓に変更することで、同じ戸籍にいるお子様方の氏も一緒に変わります。結合姓を希望しないお子様は、分籍の手続きや外国人親の氏への変更の手続きで回避することができます。
この時の分籍の手続等は、他の問題を招くことがあるので、事前に専門家に相談することをお勧めします。 -
結合姓に変更した場合、パスポートや運転免許証などの公的書類も、すべて変更しなければならないのでしょうか?パスポート、免許証などの公的証明書は、すみやかに変更の手続きをすることを強くお勧めします。また最近の本人確認の厳格化で、公的ではないもの(例えば銀行口座や携帯電話、クレジットカード等)もすみやかに変更するべきです。
-
結合姓に変更したことで、海外でのビザ申請や出入国の際に不便が生じることはあるのでしょうか?結合姓に変更したことによって、ビザ申請や出入国の際に不利になるという具体的なトラブルは、聞いたことがありません。むしろ、結合姓を使用していることで婚姻関係が明確になり、現地での手続きがスムーズになるケースもあります。
一方、日本の戸籍の氏と現地の証明書の氏が一致しないことで、煩雑さや不便の原因になることがあります。そのため、氏を統一しておくことで、将来的な手続きの簡素化が期待できます。 -
一度、結合姓にした後、やはり元の氏に戻したいと希望した場合、手続きはできますか?裁判所の許可を得て結合姓に変更した後に、原則として元の氏に戻すことはできません。ただし、離婚をされた場合は、あらためて裁判所の許可を得ることで、元の氏に変更することができます。