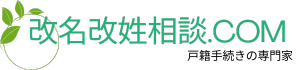改姓・氏の変更手続きでお困りの皆さまへ、当事務所は、氏名変更・戸籍訂正専門の司法書士が、日本国内外の日本戸籍をお持ちの方からのご相談を承っております。手続きの始まりから終わりまでサポートいたします。海外からのご相談も、オンラインで対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。
面談(事務所・オンライン)、メールでのご相談が可能です。なお、法律専門家の方からのご質問・ご相談は有償で対応いたしますので、資格と事務所名を明記したうえでご連絡ください。
改姓手続きの相談について
改姓手続きのご相談では事情をうかがいながら必要な資料の有無を確認して、裁判所で許可される見込みがあるかどうか、他の手続きで目的を達成することができないか、をご案内しています。
当事務所では、申立書等の具体的な記入指導や、既にご自身で申立てをされた後の裁判所対応に関するご相談・質問は承っておりません。
改姓手続きの基本について
氏を変更するためには、「やむを得ない事由」が必要です。(戸籍法107条1項)過去の裁判例や戸籍先例等で、どういった事情が「やむを得ない事由」に該当するのか、あるいは該当しないのか、概ね明確になっています。
改姓の場合は改名と違い、厳格に判断され裁判例や戸籍先例で認められる事情以外はほとんど認められませんが、裁判例・戸籍先例の理論に沿った趣旨であれば認められる余地があります。
司法書士に改姓手続きを依頼するメリット
この手続きを依頼する専門家は、弁護士又は司法書士です。弁護士に依頼する場合は、弁護士が手続代理人となって裁判所の対応を代理します。司法書士の場合は、書類作成をした専門家と扱われ、代理人ではありません。これは裁判所の面談(審尋期日)に決定的な違いがあります。弁護士は手続代理人として裁判所の面談の場に立ち会いますが、司法書士は代理人として立ち会うことができません。
私は、戸籍法や裁判例・戸籍先例の解釈を裁判所と争い、家庭裁判所から却下された後、高等裁判所、最高裁判所へ手続きを進める場合は、弁護士に依頼することが間違いなく良いと思います。逆に過去の例から考えて、家庭裁判所でほぼ許可されるであろうという場合は、ご本人で手続きをするのも良い選択だと考えています。しかし、法律的な手続きや裁判所・役所が苦手であるといった方は、司法書士に依頼するのも良いと思います。
弁護士も司法書士も、改姓・改名等の戸籍手続きを専門としている方は稀です。そのため、戸籍に関する家庭裁判所・市区町村・法務局の手続きの経験が豊富で、相談時に丁寧な説明があるか、料金体系が明確かなどを確認し、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。
相談について
ご相談は完全予約制としています。相談の日時を決めたのち、30分から1時間程度、お話をうかがいます。お話をうかがったうえで、許可の見込みや用意しなければならない資料等の説明をし、手続きの方針をご案内します。
初回の相談料は無料です。2回目以降は、1回あたり5,500円(税込)の相談料を頂戴します。
メールでのご相談の場合は、手続きの方針の概要が決まるまでを初回の相談としています。
相談のご予約について
ご相談の予約は、お問い合わせフォームからご連絡ください。電話でのお問い合わせ又は相談は現在受け付けていません。
お問い合わせフォームご相談時の持ち物について
以下の証明書等をご用意いただくとご相談がスムーズに進みます。身分証明書以外はコピーでも構いませんので、可能な限りご用意いただけると、とても助かります。
- 写真付き身分証明書
- 本籍記載の住民票
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 氏の変更の理由を証明できる資料(ないこともあります)
- 新しい氏を通称氏として名乗っている場合は、その資料(郵便物、メール、ライン等や職場の書類等)
ご相談でおうかがいすること
改姓の手続きの相談の際におうかがいするポイントはいくつかあります。
- 結婚・離婚、養子縁組等で今までに変わってきた氏の変遷
- 過去に裁判所の許可を得て氏を変更したことがあるかどうか
- 氏を変更したい理由、氏を変更しなければならない理由
1つ目の「結婚・離婚、養子縁組等で今までに変わってきた氏の変遷」は、裁判所の手続きではなく婚姻届等、役所の届出のみで氏の変更をしているかをうかがっています。家族関係の変動によって一度名乗った過去の氏への変更は、無関係な氏とは異なり許可される場合があります。ご依頼いただく際は戸籍等で事実関係を確認しますが、ご相談時にはおおよその時期と氏が分かれば大丈夫です。
2つ目の「過去に裁判所の許可を得て氏を変更したことがあるかどうか」は、過去に裁判所の許可を得て氏を変更している場合、これが原因で裁判所の許可を得られないことがあるからです。
3つ目は、「氏を変更したい理由、氏を変更しなければならない理由」です。ご本人が考えている理由以外の理由で許可を得られることもあります。裁判所には理由を裏付ける資料を提出する必要がありますが、ご相談時には具体的な資料が用意できなくても問題ありません。
オンライン相談と夜間・土日祝日のご相談
オンライン相談について
遠方に住んでいる、移動に不安がある等の理由がある方に向けて、オンラインでの相談を受けています。アプリはTeams,Zoom又はSkypeのいずれかのアプリを使用します。ご希望のアプリがあればお問い合わせ際にお知らせください。
事務所に来所いただく場合と同様に完全予約制としています。問合せの際にオンラインでの相談をご希望であることをお伝えください。海外の方で大きな時差がある場合でも可能な限り対応していますので、お気軽にご相談ください。
夜間・土日祝日のご相談について
月曜日、水曜日、金曜日の夜は、時間外の対応が可能なこともあります。お問い合わせ時に日時を確認してください。
土日祝日のご相談は、現在お受けしていません。平日のご都合が難しい場合は、オンライン相談や夜間相談をご検討ください
お問い合わせフォーム司法書士が提供するサポート内容
司法書士は家庭裁判所の手続きの代理人とはなれませんが、書類作成等を通して改姓の手続きを全面的にサポートいたします。
必要書類の収集とアドバイス・申立書の作成
ご相談の際にうかがった事情と証拠資料を確認して、裁判所に提出する申立書やその他に必要な書類を作成します。また、戸籍等の証明書の取得代行や、証拠資料の収集についてのアドバイスもいたします。
この他に例えば、裁判手続きの前に市区町村の戸籍手続きが必要な場合のサポートや、市区町村担当者と打ち合わせが必要な場合に対応しています。
作成した申立書等をご確認いただき、署名押印をお願いいたします。
裁判所への書類提出の代行
署名押印をいただいた申立書等をお預かりして、司法書士が裁判所へ提出します。
裁判所への同行
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の首都圏の裁判所へ出頭する際は、司法書士が同行します。これ以外の地域の方はご相談ください。
裁判所への出頭の必要がなく、書類でのやり取りになる場合も、書類対応のアドバイスをしています。
手続き完了後のサポート
裁判所の手続きが終わった後の氏の変更届等の手続きについてもサポートします。
銀行や携帯電話会社等の名義変更手続対応はサポート対象外です。ただし、銀行等に提出する戸籍等の証明書についてはサポートしています(別途戸籍を取得するための委任状が必要になります)。
ご依頼の流れ
ご相談後、許可される見込みがある場合は、委任契約書に署名をいただいて、必要書類の収集や申立書の作成に取り掛かります。
ご契約について
ご契約をいただく際は、ご本人確認をさせていただきます。対面でのご契約では写真付き身分証明書を確認させていただきます。遠方にお住いの場合は本人限定受取郵便等で対応しています。
費用のお支払いについて
費用・報酬のお支払いは、現金、振込、クレジットカード又は日本国内の電子マネーに対応しています。
費用・報酬のお支払いのタイミングは、書類作成報酬型の契約か着手金・成功報酬型の契約かで違います。
- 書類作成報酬型の契約の場合:裁判所に申立てをするまで
- 着手金成功報酬型の契約場合:
- 着手金と実費:委任契約後すみやかに
- 成功報酬:裁判所の許可を得た後すみやかに
途中でのご解約について
途中での解約は可能です。既に取り寄せた必要書類の実費は請求しています。また裁判所に申立てをした後等、報酬の返金をお断りすることがあります。
よくある質問(FAQ)
-
改姓の相談をしたいのですが、どうすれば良いですか?ご相談は、完全予約制としています。お問合わせフォームからご希望の日時と来所しての面談又はオンラインの相談の予約をお願いしています。
-
海外に住んでいますが、改姓手続きはできますか?海外在住の方のご依頼も多数受けています。具体的な手続きの進行はお住まいの地域等で違いがありますので、ご相談の際に現在の状況を教えてださい。
-
相談料はいくらですか?初回相談は無料ですか?初回の相談料は無料です。2回目以降は1回あたり5,500円をいただいています。
-
メール・オンライン相談は可能ですか?オンラインの相談は来所いただく場合と同じく事前に予約をお願いしています。お問合わせフォームからご希望の日時を押してください。またメールでの相談も承っています。
-
夜間や土日祝日の相談は可能ですか?毎週月曜日、水曜日、金曜日は夜間の対応が可能です。予約の際に夜間対応ご希望であることを教えてください。土日祝日は、現在対応しておりません。都合がつかないときは、夜間のご相談をご検討ください。
-
相談の際には何を持参すればいいですか?相談の際は、以下の資料を確認させてください。
- 写真付き身分証明書
- 本籍記載の住民票
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 氏の変更の理由を証明できる資料(ないこともあります)
- 新しい氏を通称氏として名乗っている場合は、その資料(郵便物、メール、ライン等や職場の書類等)